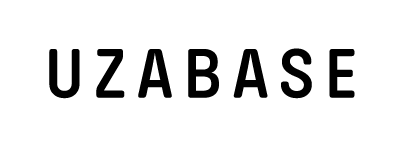構築から運用まで手間いらず:ユーザベースが語るFivetran採用の決定打
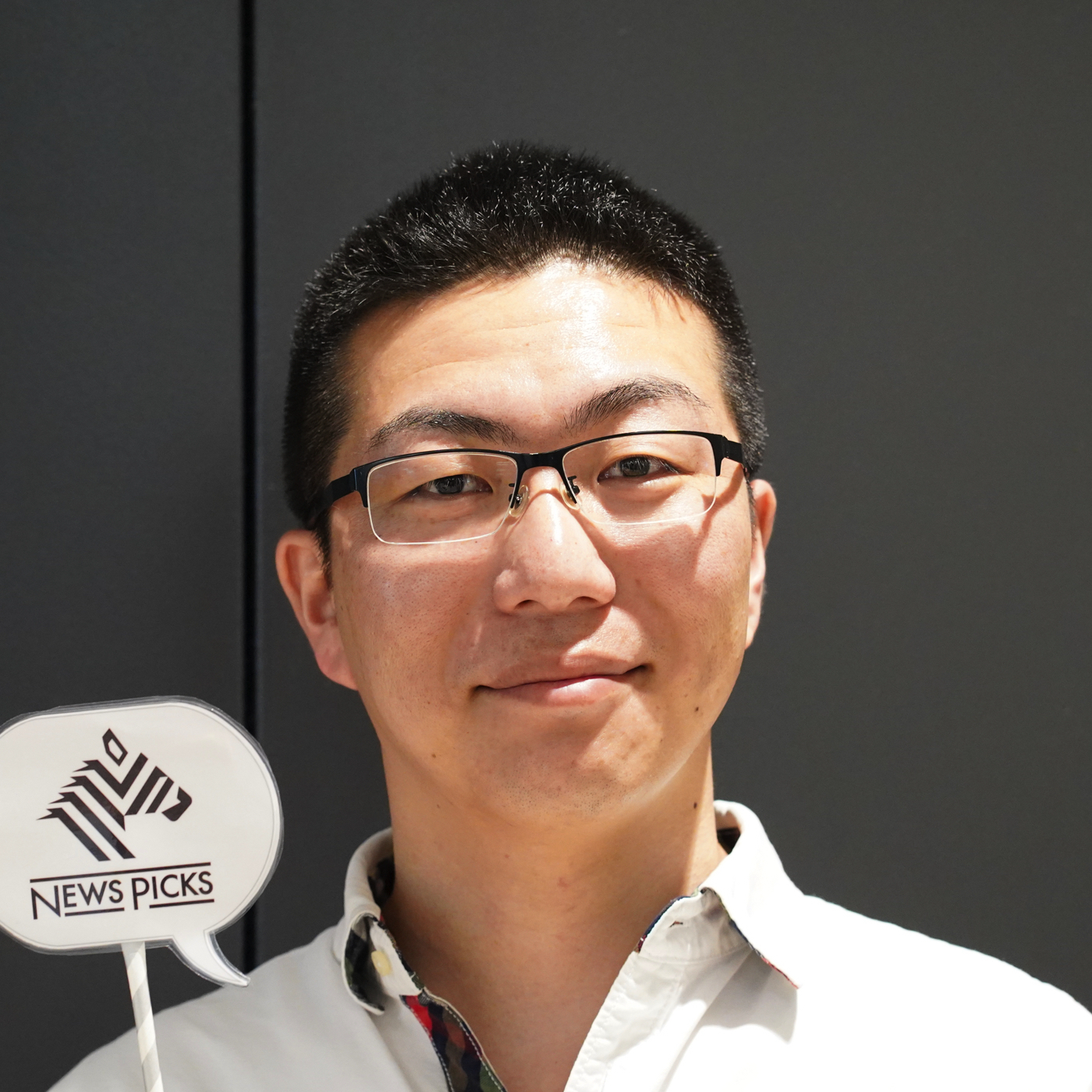
株式会社ユーザベース / 高山 温
チームリーダー / データエンジニア
| 利用プラン | 利用機能 | ツールの利用規模 | ツールの利用開始時期 | 事業形態 |
|---|---|---|---|---|
Standard | データ連係機能 | 10名以下 | 2023年5月 | B to B |
| 利用プラン | Standard |
|---|---|
| 利用機能 | データ連係機能 |
| ツールの利用規模 | 10名以下 |
| ツールの利用開始時期 | 2023年5月 |
| 事業形態 | B to B |
アーキテクチャ
アーキテクチャの意図・工夫
DWHにはSnowflakeを採用し、データの利活用とガバナンスの両立のため、source層とnormalized層というレイヤー構造を構築しました。 Fivetranで取り込まれた生データはsource層に格納されます。ここには機密性の高いカラムなども含まれます。 normalized層はsource層に対するビューとして定義され、データ利用者はこの層を通じてデータにアクセスする設計としました。
データの取り込み手段は当初Fivetranのみでしたが、特定のロジックや柔軟性のため、現在はAirflowを用いた自前PythonスクリプトとFivetranをデータ特性に応じて使い分けるハイブリッド構成へと進化しています。
導入の背景・解決したかった問題
導入背景
Fivetran導入前(データ基盤構築前)の課題
ユーザベースはスピーダとNewsPicksという2つのサービスを主に展開していますが、本記事のデータ基盤はサービスデータではなく、主に社内向けに業務SaaSのデータを格納する目的で始動しました。
当社の業務は(例に漏れず)多数のSaaSに支えられています。しかし、便利な反面データは各所に散らばり、アカウントを持つメンバーしか扱えないという状況でした。
具体的な非効率として、担当者が各種SaaSからデータをダウンロードし、スプレッドシート上で手動の結合や加工を行う業務が大量にありました。
この手作業は時間を要し、ヒューマンエラーのリスクを伴いました。データの信頼性も問題となり、迅速な経営判断のボトルネックになっていました。
どのような状態を目指していたか
目指していたのは、データ活用における停滞の解消です。データが扱いにくいため活用が進まないという負のスパイラルを断ち切りたかったのです。
最も重視したのは、「データを活用できた」という初期の成果を、できるだけ早く社内に生み出すことでした。
これにより、データ基盤の価値を早期に証明し、全社的なデータ利用の定着と好循環を生み出すことを目標としました。
比較検討したサービス
- Trocco
- Airbyte
- 内製
比較した軸
データ基盤の初期立ち上げフェーズでは、エンジニアリングリソースが非常に希少でした。
このため、内製やオープンソースの運用に貴重なリソースを割かず、「迅速な導入と工数最小化」を最優先しました。
第一の要件は、すぐに利用開始でき、運用負荷を最小限に抑えられるマネージドサービスであることでした。
特に、SaaS側のAPI仕様変更に自動で追従する信頼性と、迅速なコネクタ設定による初期導入の容易さを重要視しました。
選定理由
初期検証で最も重要視していたSalesforceからのデータ取り込みが、設定の容易さから短期間で実現できたことが最大の決め手となりました。
これは、複雑な設定や追加の開発なしに、すぐに実稼働レベルのデータパイプラインを構築できるFivetranの導入の容易さを証明しました。
また、Salesforce以外の主要な社内SaaSに対しても豊富なコネクタが網羅的に対応しており、導入の確信を深めました。
これにより、貴重なエンジニアリングリソースをパイプライン構築に割くことなく、複数のデータソースを短期間で網羅できると判断しました。
導入の成果
改善したかった課題はどれくらい解決されたか
Fivetranの導入により、以前課題となっていた手動の「スプシワーク」は、個別のユースケースにおいては完全に解消されました。 特に定型的な月次レポート業務などでは、データの抽出と統合にかかる工数を大幅に削減できています。 接続されたデータソースの種類が増えるに従い、恩恵を受ける社内メンバーが加速度的に拡大しているのを実感しています。
どのような成果が得られたか
データ連携のボトルネックが解消され、新たなデータ取り込みの要望があっても、Fivetranを使って迅速に試行し、ほとんど問題なく取り込みを開始できるようになりました。
立ち上げフェーズが終わり、社内で使うあらゆるツールに格納されたデータを一つのデータ基盤に集約してデータ・AI活用のハブにするという目標を現実的に持てるようになってきました。
導入時の苦労・悩み
Fivetranの導入自体はスムーズでしたが、一部で技術的な調整が必要な課題も発生しました。
特に苦労したのは、SaaS側で設定されたカラム名が日本語だった場合の挙動です。
取り込み元のカラム名が日本語だった場合に、カタカナのローマ字表記と漢字のピンインが混ざった読みにくい文字列に変換されてしまう問題が発生しました。 この課題に対し、Fivetranの管理APIを活用し、変換後のカラム名と元の日本語カラム名のマッピング情報を取得しました。
データウェアハウスへの取り込み後のデータ変換レイヤー(後述)で、このマッピング情報を基にカラム名を正式なものに変換することで問題を解決しました。
導入に向けた社内への説明
上長・チームへの説明
導入に際し、上長や経営陣には主に人件費の観点から費用対効果を説明しました。
手動での「スプシワーク」に費やされている膨大な時間をデータ基盤の自動化で削減できる費用を具体的なROIとして算出し、導入の正当性を主張しました。
Fivetranの費用体系は従量課金モデルのため、初期段階で高額な固定費は不要でした。この低コストでのスタートが可能だった点が、導入のハードルを下げる要因となりました。
活用方法
Fivetranは、日常的な運用においてデータエンジニアリングチームの介入頻度が低い状態を実現しています。
新規コネクタの追加は月に1個程度のペースです。追加から14日間は課金対象外となるため、この期間をコストとデータスキーマの検証期間として活用しています。
一度運用が開始されると、SaaS側のAPI変更などによるパイプラインの保守作業は実質ゼロになりました。
同期遅延や障害は自動でメール通知され、ほとんどの場合Fivetran側でしばらくすると自動的に解消されるため、手動での介入はほとんど不要です。
よく使う機能
現在、Fivetranで利用している機能の核は、SaaSアプリケーションからのデータ取り込み機能に集約されています。
一度設定すればSaaS側のAPI仕様変更などに対する自動メンテナンスがなされる点は、エンジニアリングリソースの節約に大きく貢献しています。
その他の機能(Fivetranがdbtで定番のデータ変換をしてくれるTransformations、オンプレデータ取り込みのHVR、Connector SDKなど)は、現時点では導入の対象外。
ツールの良い点
運用負荷の低さ: SaaS側のAPI変更やバージョンアップにFivetranが自動で追従するため、データパイプラインの保守・運用工数が実質ゼロになった
米国製の主要SaaSのコネクターが充実: 社内の主要な業務ツールに対するコネクタが最初から整備されており、データ点在の課題を短期間で解消できた
コネクターごとに14日間の無料期間がある: コストを抑えながらアジャイルにデータ連携を試行できる
問い合わせの体験が非常に良い: サポートへの問い合わせ時に直近のエラー情報などを自動で取得してくれるなど、問い合わせの流れが製品と一体化して非常に洗練されています。返信も早いし的確だ
ツールの課題点
日本製SaaSのコネクターが皆無
日本語カラム名が読みにくい形で連携される(前述の通り)
コストが予期せず高騰するリスク: 課金体系は月間で取り込まれた行数(MAR)に対する従量課金のため、取り込み元のデータで大量の変更が発生した場合、コストが跳ね上がるリスクがある
コネクターによる差分取り込みの対応状況の違い: 一部のコネクターは差分取り込みに対応しておらず、同期のたびに全件取り込みが発生し、コスト増の要因となるケースがあった(2025年3月からは大幅に解消されたそうだが、未検証)
ツールを検討されている方へ
データ連携ツールの導入を検討されている技術者の方に伝えたいのは、リソース配分の最適化という視点です。
データ基盤構築フェーズにおいて、内製によるパイプラインの保守・運用に時間を費やすことを避け、データ活用に集中することを選びました。
Fivetranは「専任の優秀なエンジニアチームが常駐しているような安心感」を提供してくれます。障害対応やSaaS仕様変更の懸念から解放され、総合的に運用負荷の低いサービスだと感じています。
特に、エンジニアリソースが希少な組織や、データ活用の文化を迅速に立ち上げたい企業に強くお勧めします。
今後の展望
Fivetranの日本法人も設立されたため、今後もし日本製SaaSのコネクターが増えれば、国内業務データの集約が容易になり、サービスの使い勝手は飛躍的に向上すると期待しています。
ユーザベースにおいては、今後もFivetranを便利に活用しつつ、Airflowなどを用いた内製化も推進していきます。
これにより、社内のデータが集約され、データ・AI活用のハブとなるデータ基盤としての役割をさらに強化していくことを目標としています。
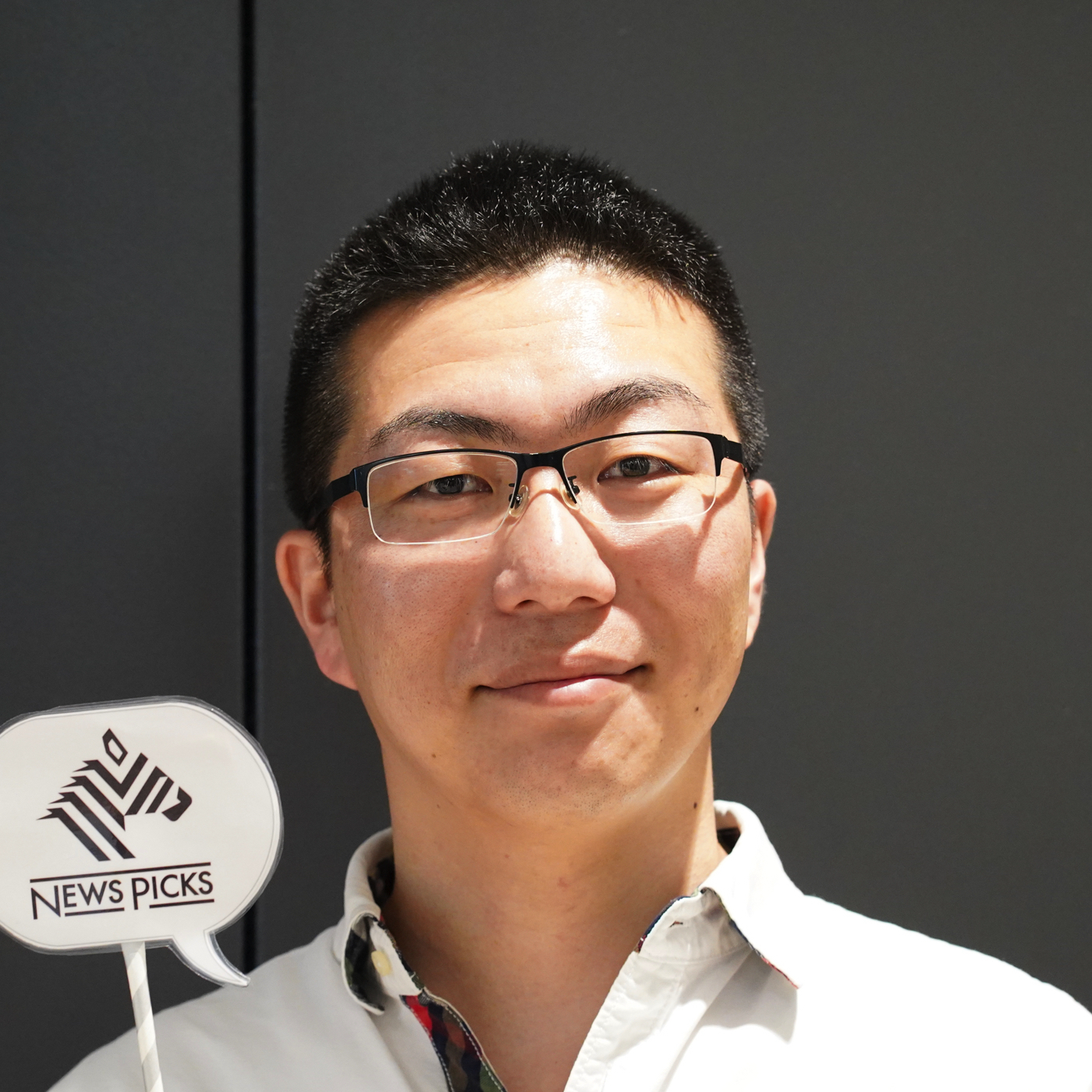
株式会社ユーザベース / 高山 温
チームリーダー / データエンジニア
よく見られているレビュー
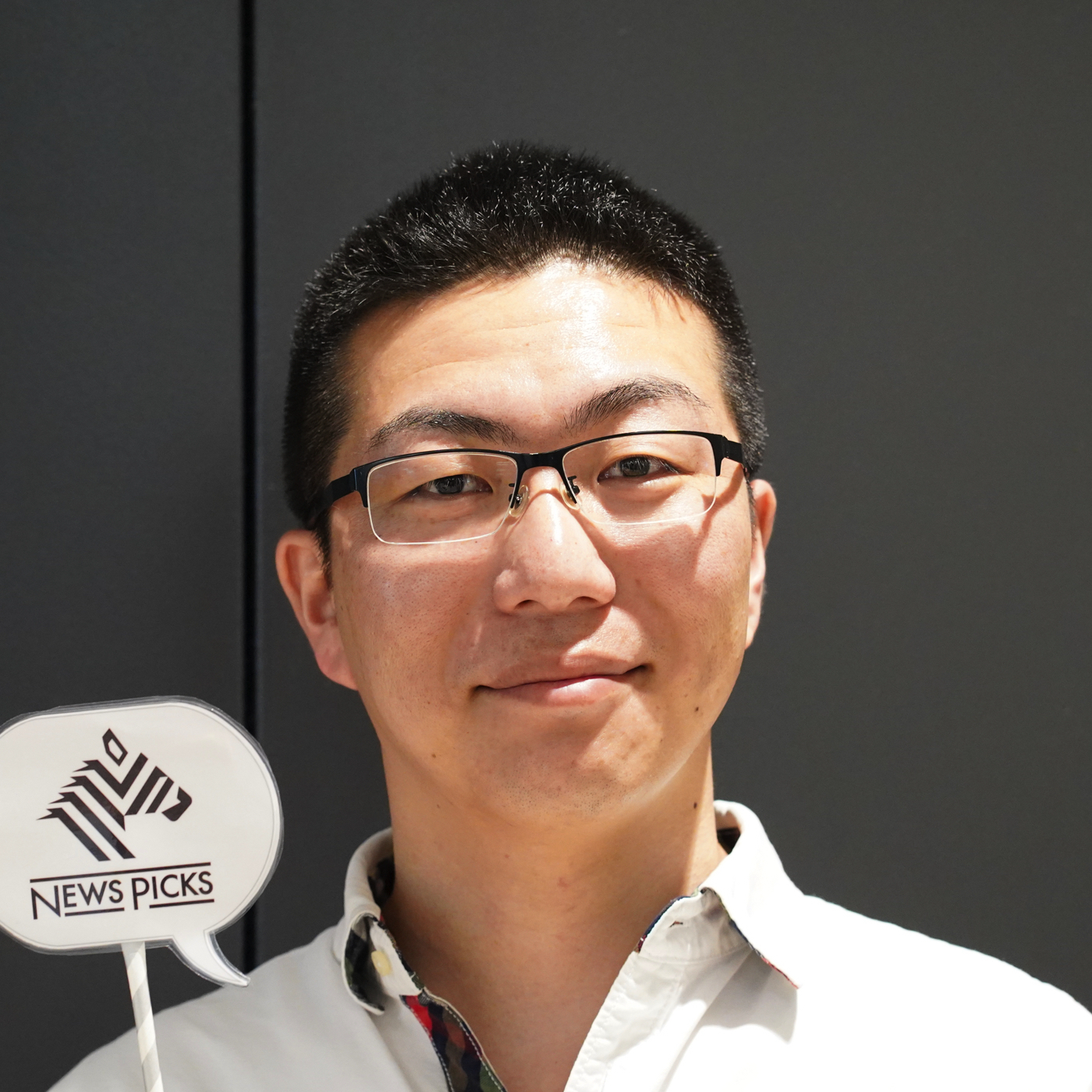
株式会社ユーザベース / 高山 温
チームリーダー / データエンジニア
レビューしているツール
目次
- アーキテクチャ
- 導入の背景・解決したかった問題
- 活用方法