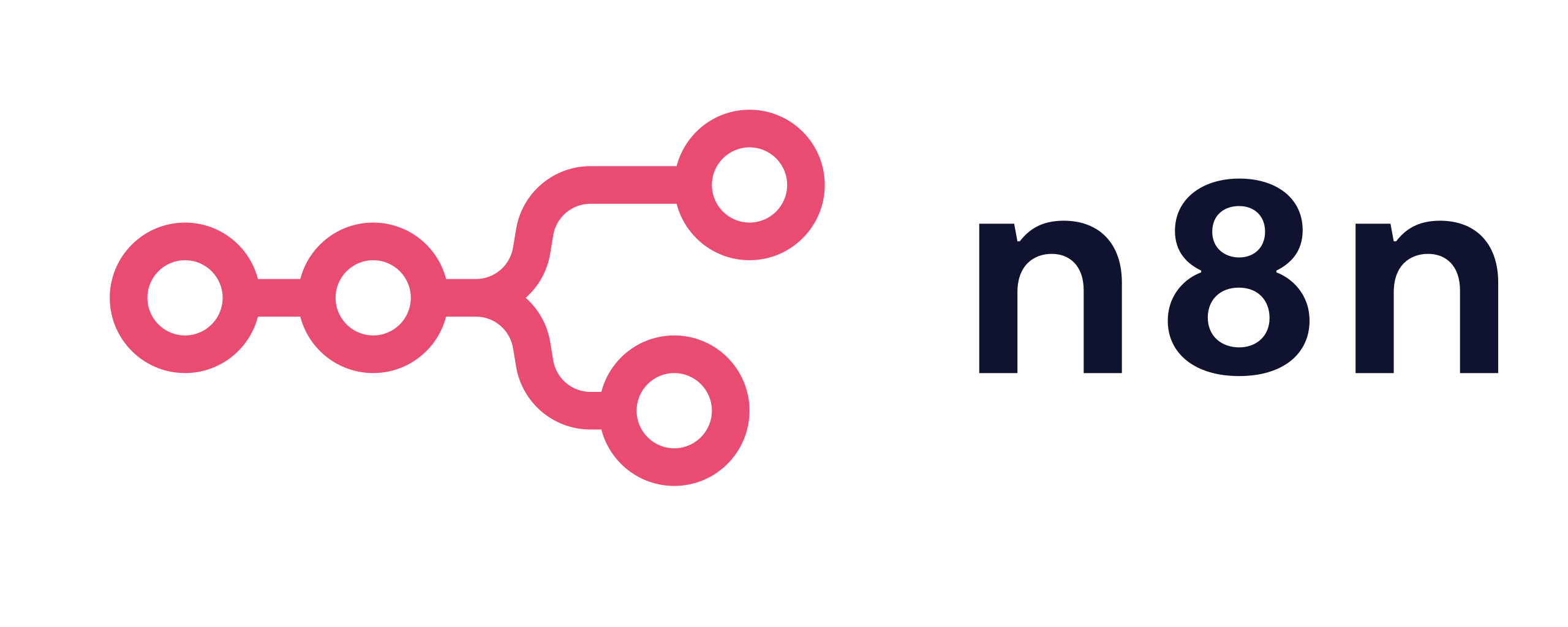n8nでノーコードで「自律型AIエージェント」を開発する
ノバセル株式会社 / yujiosaka
CTO・VPoE / CTO / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 11名〜50名
| 利用プラン | 利用機能 | ツールの利用規模 | ツールの利用開始時期 | 事業形態 |
|---|---|---|---|---|
Community Edition | AIワークフロー構築・自動化 | 11名〜50名 | 2025年3月 | B to B |
| 利用プラン | Community Edition |
|---|---|
| 利用機能 | AIワークフロー構築・自動化 |
| ツールの利用規模 | 11名〜50名 |
| ツールの利用開始時期 | 2025年3月 |
| 事業形態 | B to B |
アーキテクチャ
アーキテクチャの意図・工夫
このアーキテクチャは、インフラ運用の課題(EOL直前対応、CVE通知ノイズによる負荷)を解決するために設計しました。
Google Sheetsで管理しているシステム台帳(使用中のミドルウェアやライブラリのバージョン、CPE情報など)をデータソースとし、n8nが毎日定時に外部API(endoflife.date, NVD API)と連携して情報をチェックします。
工夫した最大のポイントは、処理の中心にAI Agentノードを活用している点です。従来、複雑な条件分岐(例:「新しい脆弱性が発見されたか」「EOLまで90日を切ったか」「ステータスが対応中(upgrading/suspended)なら通知を抑制するか」など)をノーコードで実装すると多数のIFノードが必要になり、保守性が低下します。
AI Agentにこれらのロジックを自然言語(プロンプト)で指示することで、ワークフローを簡潔に保っています。これにより、意味のある変化があった場合のみ、Slackに通知されるようになり、通知ノイズを大幅に削減できました。
導入の背景・解決したかった問題
導入背景
時系列
- 比較開始(2025年1月)
- 正式導入(2025年3月)
ツール導入前の課題
当時、特定の差し迫った課題があったわけではありませんでしたが、社内では常に新しい技術を活用して業務効率化やシステム監視の仕組みを改善しようという動きがありました。
特にAI技術の進展に伴い、「便利そうだから試してみよう」という探究心から、これらの自動化をさらに高度化できるノーコード・ローコードツールに注目が集まっていました。
どのような状態を目指していたか
日常の定型業務を効率化するだけでなく、将来的にAIエージェントをバックエンドとして活用し、自律的に判断・実行できるシステムの構築を目指していました。
特に、エンジニアが直感的に使え、必要に応じてコードを書いて機能を拡張できるエンジニアフレンドリーなプラットフォームであることが重要でした。
比較検討したサービス
比較した軸
- エンジニアにとっての使いやすさ:複雑なワークフローを組む際や、細かい制御が必要な場合に、直感的に操作できるか
- 柔軟性と拡張性:JavaScriptやPythonでのコーディングが可能か、外部パッケージを自由に利用できるか
- ワークフロー制御機能:ループ処理、条件分岐、エラーハンドリングなど、自動化ツールとしての基本的な機能が成熟しているか
選定理由
最終的にn8nを選択した決め手は、その高い柔軟性とエンジニアフレンドリーな設計でした。
日本語の情報はDifyの方が多かったのですが、実際にエンジニア数名で試用したところ、n8nの方がノードベースのUIで視覚的にワークフローの流れを追いやすく、直感的に使えると好評でした。
また、n8nはAIが登場する以前からワークフロー自動化ツールとしての実績があり、制御機能が非常に豊富です。複雑なワークフロー(例えばGoogle Drive上のファイルを形式によって振り分ける場合など)ではコードを書く必要が出てきますが、n8nではJavaScriptやPythonのコードを柔軟に実行でき、外部パッケージも利用できる点が大きな魅力でした。
比較検討の初期段階(2025年1月)ではDifyにAgentノードがまだなかったことも影響しましたが(Difyは2025年9月に導入)、その時点ではすでにn8nの機能的優位性を感じており、導入を決定しました。
導入の成果
改善したかった課題はどれくらい解決されたか
導入目的であった日常業務の効率化や監視・アラートの高度化は、期待以上に達成されました。特に、インフラ・ミドルウェアのバージョン管理と脆弱性検知の自動化において大きな成果を上げています。
どのような成果が得られたか
従来、手動で行っていたインフラのEOL(End of Life)管理や、日々流れてくるCVE(脆弱性)通知の確認作業を自動化しました。これにより、セキュリティリスクの低減とエンジニアの工数削減を同時に達成できました。
また、AIアプリケーション開発の基盤としての成果も大きいです。私たちはAI開発において以下のフローを採用しています。
- Phase 1: MVP(n8nでワークフローを自動化し機能を実装)
- Phase 2: アプリ化(洗練したアプリを提供しUXを改善)
n8nはそのままAPIとして呼び出せるため、Phase 1からPhase 2への移行が非常にスムーズで、開発スピードが格段に向上しました。
導入時の苦労・悩み
エンジニアチームでは非常に便利に活用されていますが、非エンジニアのメンバーへの導入は思うように進みませんでした。
n8nは自由度が高い反面、ワークフローが複雑になりがちで、非エンジニアのメンバーがインターフェースを見て尻込みしてしまうケースが見られました。結果として、非エンジニア層には後から導入したDifyの方が広く使われるようになり、「エンジニア向けのn8n、非エンジニア向けのDify」という棲み分けが進みました。
また、Difyと比較して日本語の情報が少なかったため、導入初期は英語のドキュメントやコミュニティを参照する必要がありました。
導入に向けた社内への説明
上長・チームへの説明
OSS(Community Edition)を利用するためライセンス費用がかからない点を強調しつつ、以下の点をメンバーに説明しました。
- MVP開発の高速化:ノーコード・ローコードで迅速に自動化ワークフローを構築し、仮説検証サイクルを早められること
- 将来的な拡張性:n8nのワークフローはAPIとして直接呼び出せるため、将来的にアプリケーション化する際にも、バックエンド(API、MCPサーバー等)としてそのまま活用でき、コードで書き直す必要がないこと
- 具体的な工数削減効果:煩雑だったインフラの脆弱性管理などを自動化するプロトタイプを提示し、工数削減とリスク低減効果を示しました
活用方法
エンジニアチームを中心に、以下のような用途で日常的に利用しています。
- 監視・アラート: 上記のインフラ管理のほか、各種システムのメトリクス監視と異常検知
- 日常業務の効率化: 定期的なレポート作成、スプレッドシート間のデータ同期、週報の自動生成など
- 簡易MCPサーバー: MCP Serverトリガーを受け取り、別のサービスに連携するハブとして
- AIエージェントのバックエンド: Anthropicが提唱するBuilding Effective AI Agentsの概念(Prompt chaining, Routing, Parallelizationなど)を参考に、複雑なAIエージェントロジックを構築している
よく使う機能
- AI Agentノード: 複雑な処理ロジックを自然言語で記述できるため、多用している
- Google Sheets連携 / HTTP Request: 社内データや外部サービスとの連携
- Codeノード (JavaScript/Python): 標準ノードだけでは足りないデータ整形や複雑な計算、外部パッケージの利用を行う際に使用
ツールの良い点
- 高い柔軟性と拡張性: ワークフロー制御機能が豊富で、JavaScript/Pythonコードも実行できるため、非常に複雑な自動化も実現可能
- エンジニアフレンドリーなUI: ノードベースのUIは視覚的に分かりやすく、エンジニアにとって直感的に操作できる
- 強力なAIエージェント機能: AI Agentノードにより、LLMを活用した高度な判断や処理が容易に実装できる
- APIとしての利用: 作成したワークフローを簡単にAPI化でき、外部システムのバックエンドとしても優秀
- セルフホスト可能: OSSとして提供されており、コストを抑えて自社環境にセキュアに構築できる
ツールの課題点
- 非エンジニアには学習コストが高い: 自由度が高い反面、機能が多く複雑なため、非エンジニアが使いこなすには時間がかかり、実際、非エンジニア層にはDifyの方が広く使われている
- 日本語情報の不足: Difyなどと比較すると、日本語のドキュメントや事例がまだ少ない
ツールを検討されている方へ
n8nは、エンジニアが主導して複雑な業務自動化やAIエージェント開発に取り組む場合に最適なツールです。高い柔軟性と拡張性を求めるチームには強くお勧めします。特に、既存のシステム間の連携や、コードを書いてでも柔軟な自動化を実現したい場合には、非常に強力な選択肢となります。
一方で、非エンジニア中心のチームで簡単なタスク自動化を行いたい場合は、DifyやZapierなど、より学習コストの低いツールを検討する方がスムーズかもしれません。自社のチーム構成と自動化の目的に合わせて選定することが重要です。
今後の展望
今後は、n8nとDifyを明確に使い分けていく方針です。
- n8n: 複雑なワークフローをノーコード・ローコードで置き換えるための強力なバックエンド基盤として、特にAIエージェントを活用した高度な自動化はこちらで担う
- Dify: 非エンジニアのメンバーがGPTsの延長のような形で手軽にAIチャットボットや簡単なエージェントを作成するためのツールとして活用し、社内全体のAI活用を推進していく
ノバセル株式会社 / yujiosaka
CTO・VPoE / CTO / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 11名〜50名
よく見られているレビュー
ノバセル株式会社 / yujiosaka
CTO・VPoE / CTO / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 11名〜50名
レビューしているツール
目次
- アーキテクチャ
- 導入の背景・解決したかった問題
- 活用方法