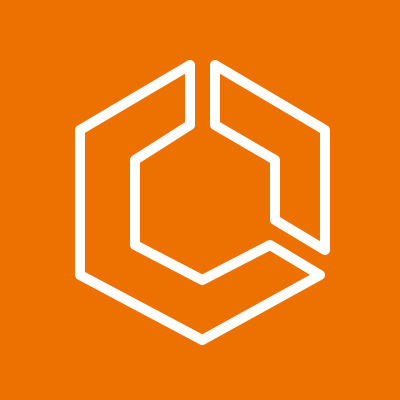責任分界を意識してEC2からECSへ移行する
株式会社ココナラ / takumi.yoshikawa
チームリーダー / インフラエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
| 利用プラン | 利用機能 | ツールの利用規模 | ツールの利用開始時期 | 事業形態 |
|---|---|---|---|---|
AWS Enterprise | ECS on EC2、ECS on Fargate | 11名〜50名 | 2021年 | B to C C to C |
| 利用プラン | AWS Enterprise |
|---|---|
| 利用機能 | ECS on EC2、ECS on Fargate |
| ツールの利用規模 | 11名〜50名 |
| ツールの利用開始時期 | 2021年 |
| 事業形態 | B to C C to C |
アーキテクチャ
アーキテクチャの意図・工夫
特別複雑なことはせず、一般的でシンプルな設計を心がけました
導入の背景・解決したかった問題
導入背景
ツール導入前の課題
- アプリケーションレイヤーで1つのアプリケーションが複数の役割を持っていた
- これを一定の役割ごとに分割することにした
どのような状態を目指していたか
- 当時EC2上で稼働していたが、状態管理が適切に行われていなかった
- そこで、適切に状態管理を行いやすい、またはそもそもその必要のないサービス上に展開することを目指した
比較検討したサービス
- EC2
- Lambda
比較した軸
- 重い処理を含むスケジュールバッチおよびapiサーバを同様の仕組みで管理できること
- サーバ管理コストができるだけかからないこと
選定理由
- EventBridgeルール/スケジューラやStepFunctionsと組み合わせて使うことでバッチ管理しやすい
- アプリケーションとインフラストラクチャの責任分界がはっきりしていること
- アプリケーション:イメージビルド、タスク定義管理
- インフラストラクチャ:ECSクラスタ/サービス管理、ドメイン設定 etc
上記の条件はLambdaも満たしているが、以下の点からECSを選択
- 複雑なアプリケーションであり、コードサイズの制限にかかった
- 長時間バッチの実行に耐えられない
- サーバ接続してコマンド実行したいユースケースが存在した
- ローカル実行環境を利用するのにクセがある
- DockerImageを利用したLambdaを利用すればおそらく解決される
導入の成果
FargateとしたケースではAnsibleによる状態管理が不要となり、インフラ管理ツールをTerraformに統一することができました。
導入時の苦労・悩み
1. 責任分界点を意識したCDパイプラインの作成
- 開発チーム:タスク定義
- インフラチーム:ECSクラスタ、サービス
というように責務を分解し、タスク定義は開発リポジトリで管理することとしました。
CircleCIでデプロイパイプラインを作成していましたが、当時はaws-ecsOrbをそのまま用いるだけではうまく想定するタスク定義が作成できなかったため、
- タスク定義をjsonで作成 -> タスク定義の登録 -> サービスの更新
という一連の流れを自前で実装しました。(おそらく記載時点ではもっとラクにできるはず)
2. 基盤の選択(EC2 or Fargate)
それぞれにメリット・デメリットがあるため、サービスによって使い分けています。一例は以下です。
- EC2
- メリット
- コストコントロールがしやすい
- 細かなチューニングを行いやすい
- Fargateの場合は制約が多い
- デメリット
- 状態を持つことになるためその管理・運用が必須となる
- メリット
- Fargate
- メリット
- サーバ運用管理コストがゼロ
- 気にしなくてもセキュリティパッチが自動で適用されるetc
- (バッチ稼働において)稼働した分だけリソースが使用される
- サーバ運用管理コストがゼロ
- デメリット
- 従量課金のため、コストコントロールがしにくい
- EC2に比べるとやや割高
- メリット
3. ブルーグリーンデプロイメントによる切り替え
もともとEC2サーバで稼働中のものをダウンタイムをとることなく、かつ不備があった場合にすぐ戻せるようにブルーグリーンデプロイ方式で移行を行いました。
4. 稼働しているFargateサーバ上への接続設定
当時は情報が少なく苦労した点の1つです。
ECSExecをサービス(タスク)側で有効にし、execute-commandコマンドによって接続することが可能です。
導入に向けた社内への説明
上長・チームへの説明
もともと他のサービスとあわせて動いていたサービスを分離するにあたって、インフラ運用コストもあわせて下げたいということの説明で納得してもらいました。
活用方法
よく使う機能
- コンテナオーケストレーション
- Container Insights
ツールの良い点
- クラスタ:サービスが1:Nであるので、1つのサービスの開発環境を1つのクラスタでまとめて管理することが可能
- タスク定義とサービス設定というレイヤーによって責務が分離されている
- カスタマイズ性が高い
ツールの課題点
- ECS on EC2 か ECS on Fargate のどちらを選択するかが難しい
ツールを検討されている方へ
Lambdaのほうがより手軽に解決することが可能ですが、制約事項も多く、のちにパフォーマンス等の最適化を行いたくなったときに苦労します。一方でECSを選択しておくと細かな実行環境設定がしたくなった場合は、基盤をFargateからEC2に変更するだけで他の設定を変更することなく実現できます。 また、近年のクラウドネイティブといえばKubernetesが筆頭ですが、学習コストおよび運用コストが非常に高く、最初のコンテナ環境として利用するにはある程度の覚悟が必要となります。
上記より、もっともバランスのとれたサービスがECSであると感じています。
株式会社ココナラ / takumi.yoshikawa
チームリーダー / インフラエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
よく見られているレビュー
株式会社ココナラ / takumi.yoshikawa
チームリーダー / インフラエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
レビューしているツール
目次
- アーキテクチャ
- 導入の背景・解決したかった問題
- 活用方法