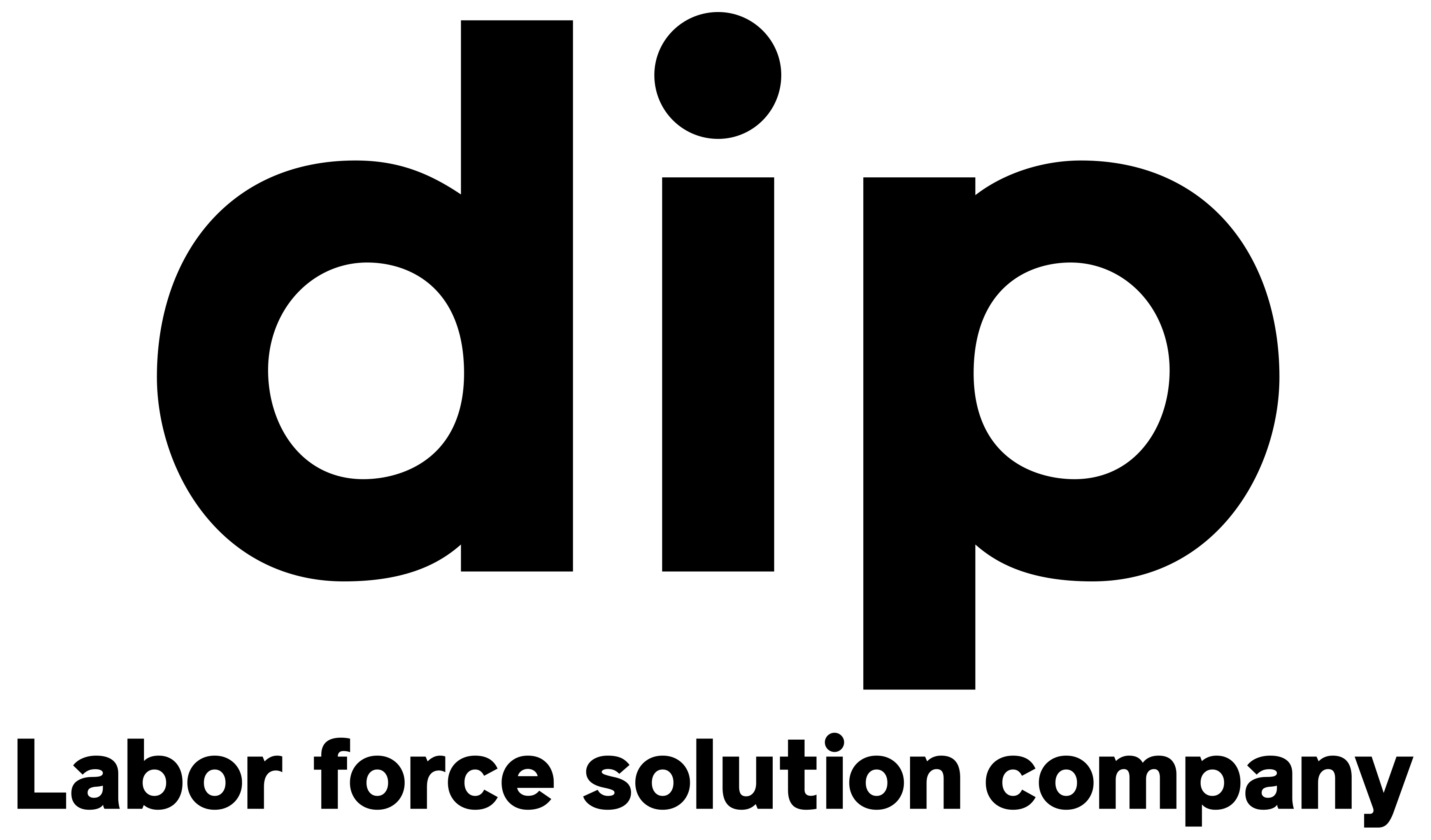ネイティブアプリプロダクトでのDevin活用事例の紹介
ディップ株式会社 / よしだま
テックリード
| 利用プラン | ツールの利用規模 |
|---|---|
Team | 101名〜300名 |
| 利用プラン | Team |
|---|---|
| ツールの利用規模 | 101名〜300名 |
導入の背景・解決したかった問題
導入背景
- 20年以上続くサービスの複雑化により認知負荷が高く、属人的な開発をしている状態でした。
- 当時の状況として、新規機能開発よりも既存機能の保守・デバッグに多くのリソースが割かれ、リリースサイクルが長期化していました。特に、サービス立ち上げ当初から在籍する一部のベテラン開発者に知識やノウハウが集中しており、これが大きなボトルネックとなっていました。
- 一部のメンバーが先行して利用しており、全社導入以前より利用することによる効果には期待できるものがあったため、全社で導入できるプランを選択し導入に踏み切りました。先行利用では、特に複雑なレガシーコードの解析や、ユニットテストの自動生成において、目覚ましい効果が確認できていました。
導入の成果
前提
- Android/iOSアプリでの活用
- ネイティブで開発している(FlutterやReact NativeやKMP/CMPではない)
- ソフトウェアアーキテクチャはGoogle推奨のもの(MVVM + 3層レイヤードアーキテクチャ)を採用
- AI向けのルールファイルが、アーキテクチャ/ユニットテスト/サブドメインモジュールなどの単位で整備されている
- Devinは最低限のセットアップをして、Knowledgeで参照するべきルールファイルのパスを伝えているだけ
という状態のアプリプロダクトで3ヶ月ほど利用した経験を基にしています。
改善したかった課題はどれくらい解決されたか
課題というより、以下のような期待感がありました。 「整備されたルールに則った、品質の高いソースコードを出力する」 「開発〜PRの作成までを自動で行う」 「人が作業するよりも早く成果物を出力する」
これによって、コーディングが自動化されることで開発効率が上がることを期待していました。 完全な自動化は期待しておらず、だいたい合っているコードを書いてくれたら良いなと考えていました。
どのような成果が得られたか
結論としては、期待していた効果は十分得られました。 レイヤードアーキテクチャにおけるDomain層, Data層でDevinの実装実績が貯まっていて、そこでの成果を紹介します。
ある程度具体的なプロンプトを作る必要はありますが、作業を開始してから5〜8分ぐらいでPRが作られます。 そこから人間の手で修正を行い、PRレビューとマージが行われます。人による修正は基本的に10分以内で終わっています。 最終的にDevinが生成したコードが6割、人間の修正が4割ぐらいの成果物がマージされる状態で安定しています。 (ちなみに1PRあたりの変更行数は、大体200〜400行です) 人間が実装すると1PRあたり 1.5〜3h かかっていた各層の実装が、Devinで6割ぐらい自動化されていて、 プロンプトの作成から人による修正までを合わせて「だいたい30分、長くて60分ぐらい」に短縮されています。
削減された時間は、タスクの整理や計画の調整、ちょっと難しい開発のペアプロなどに充てています。
その他の成果の紹介
弊社の別プロダクトでは、Slackに連携されたDevinにBizメンバーが仕様の問い合わせをするような活用もしています。一定精度の回答は得られているようです。 Slackでのやりとりは技術者も見れるので、DevinをハブにBiz/Devが一緒に課題解決をするやりとりが生まれる点も、個人的には良い効果を生み出しているなと感じています。
導入に向けた社内への説明
上長・チームへの説明
- 属人性の排除と品質の安定化: AI支援によるコード生成・レビュー・テストにより、ベテラン依存の知識を形式知化し、開発プロセスの標準化と品質の底上げを図る。
- 認知負荷の軽減と生産性向上: 複雑化したコードベースの理解にかかる時間をAIがサポートし、メンバーが本来注力すべき新しい価値の創出に集中できる環境を実現する。
- 将来的な技術負債の解消: AIが既存コードの解析とリファクタリングの提案を行うことで、長年の技術負債の解消を加速させ、サービスを再び成長軌道に乗せるための基盤を整備する。
- 早期のキャッチアップと定着: すでに一部メンバーによる先行利用で効果が確認できているため、全社導入後のスムーズな利用開始と、早期のROI(投資対効果)実現が見込めること。
活用方法
よく使う機能
- プロンプトを与えて開発作業を行ってもらう
ツールの良い点
- 任せたらPRの作成までノンストップで行ってくれる
- ネイティブアプリ開発に必要なコーディング能力は十分にある
- メソッドやモジュールという小さい単位ではなく、レイヤーレベルの開発で成果を出せている
- Slack連携が簡単で、チャットベースで動かすことが容易。非技術者の利用ハードルが低い
ツールの課題点
(課題は、その他のAIツールやLLMと同様だと感じています。)
- 指示やルールのプロンプトは一定具体的でないと出力精度は落ちる
- 精度の課題がある以上、人の目による精査は必要だし、そこを補うのであれば自動テストの整備など、地道な努力も必須
ディップ株式会社 / よしだま
テックリード
よく見られているレビュー
ディップ株式会社 / よしだま
テックリード