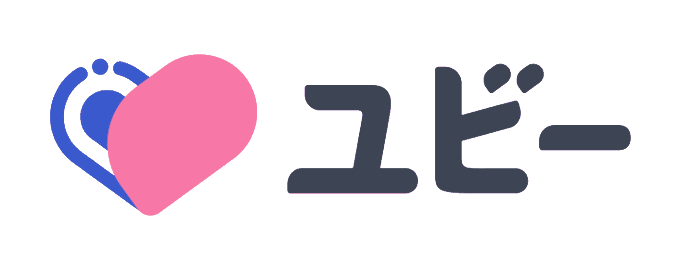Cursorの導入効果をレビューでご紹介(guchey-Ubie株式会社)
Ubie株式会社 / guchey
メンバー / フルスタックエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
| 利用プラン | ツールの利用規模 | ツールの利用開始時期 | 事業形態 |
|---|---|---|---|
Business プラン | 51名〜100名 | 2025年1月 | B to B B to C |
| 利用プラン | Business プラン |
|---|---|
| ツールの利用規模 | 51名〜100名 |
| ツールの利用開始時期 | 2025年1月 |
| 事業形態 | B to B B to C |
導入の背景・解決したかった問題
導入背景
ツール導入前の課題
当時、ChatGPTなどを活用する文化はあったものの、その用途は「困った時の質問相手」に留まっていました。開発プロセス全体にAIの支援を統合できておらず、「ほとんど手動開発しない」という理想とは程遠い状況でした。
具体的には、以下の3つの課題がありました。
- AIをコーディングのパートナーとして常時活用するまでには至らず、手動での作業が多く残っていました。
- 当時、他のAIツール(Devin, Clineなど)を試す中で、従量課金によるコストの高騰が懸念され、開発者がコストを気にせず安心して利用できる環境ではありませんでした。
- AIに的確な指示を出す上で、コードベース全体の文脈(コンテキスト)や組織、チーム、プロダクトの情報を効率的に与える仕組みが不足していました。
どのような状態を目指していたか
上記の課題を解決し、以下の2つの状態を目指しました。
- 「ほとんど手動開発しない」体験を実現。コーディングの定型業務をAIに任せ、開発者がより創造的で本質的な課題解決に集中できる状態。 月額$40のコストに対し、エンジニア一人あたり月1時間以上の工数削減効果を生み出すなど、投資対効果を明確に上回る生産性向上。
- 専門外の言語や技術であっても、AIの支援で開発に着手できる状態。QAエンジニアやデザイナーなど、エンジニア以外の職種も開発プロセスへ容易に参加し、組織全体のアウトプットを最大化できる状態。
比較検討したサービス
- Cline
- Devin
- Github Copilot
比較した軸
ツール選定にあたり、以下の3つの点を重要な比較軸としました。
コストの予測可能性と管理のしやすさ
当時他の従量課金制ツールと異なり、Cursorは一人当たり月額$40の固定料金でした。これにより、予算が立てやすく、開発者がコストを気にせずAI機能を試せる心理的安全性を確保できる点を高く評価しました。また、40名規模での利用を想定していたため、Businessプランで課金を集約できることも管理上必須の要件でした。
開発体験の質とAIとの統合度
単なるコード補完に留まらず、エディタが持つ様々なコンテキスト情報をAIに簡単に与えられる点を重視しました。これにより、AIがコードベースの文脈を深く理解し、より的確な支援を提供できる「AIを基礎とした開発体験」が実現できると考えました。
組織利用における管理・統制機能
企業として導入する上で、ガバナンスを確保できるかどうかも重要な選定基準でした。Businessプランの「プライバシーモードを中央集権的にオンにできる」機能は、ソースコードという機密情報を扱う上で不可欠でした。
選定理由
最終的にCursor Businessの導入を決定づけたのは、以下の3点です。
コストの予測可能性と心理的安全性
利用量に応じてコストが変動する他ツールと違い、固定料金制であるため「課金に心配しすぎないで済む」という安心感が最大の決め手でした。これにより、開発者がコストを気にせず試行錯誤できる環境が作れると判断しました。
AIと深く統合された、質の高い開発体験
エディタの文脈をシームレスにAIへ連携できるため、生産性を大きく飛躍させられるポテンシャルを感じました。「ほとんど手動開発しない」という理想の体験を追求できる点が魅力的でした。MCPのサポートで社内のドキュメント(Notion / JIRA / Figma)のコンテキストを与えることができ、生成されるコードの品質が上がったとも感じます。
組織規模に適した管理・統制機能
利用希望者が40名規模と多かったため、個人契約では管理が煩雑になると判断しました。「課金の一元管理」と「プライバシーモードの強制」という、組織運用に必須の機能を備えていたことが導入を後押ししました。
導入の成果
どのような成果が得られたか
- プロダクト開発、インフラ、データ分析など様々な領域で「効果を実感」する声が上がっており、日々の業務効率が向上しています。月額$40のコストに対し、月1時間以上の工数削減効果は十分に得られている手応えがあり、投資対効果の高い施策であったと評価しています。
- 「スキル制約開放」という新たな価値の創出、これが最も大きな成果の一つです。普段使わない言語(Go)でも、AIの支援でツールを実装できるようになりました。QAエンジニアがテストコード開発に参加するなど、これまで開発に直接関わることが難しかったメンバーも、開発プロセスに直接貢献できるようになりました。 これにより、組織全体のアイデアや発想の幅が広がるという、生産性向上とは別の重要なリターンが得られました。
- オンボーディングや情報共有を通じて、「先進的な取り組み」としてAI活用をチームで楽しむ前向きな雰囲気が生まれました。「AI活用を諦めない」という組織的なコミットメントが生まれ、課題に直面してもチームで乗り越えていこうというカルチャーが形成されつつあります。エンジニアの利用している様子を見て非エンジニアが新しい活用方法を探索するなど、広がりはエンジニアの枠を超えています。
導入に向けた社内への説明
上長・チームへの説明
導入にあたり、特に費用対効果とセキュリティについては、以下の点を重点的に説明しました。
明確なROI
「一人当たり月額$40」というコストに対し、「ハイクラスのエンジニアが月に1時間強の生産性を向上させれば十分に元が取れる」と具体的な損益分岐点を示し、投資対効果の高さを訴求しました。
コスト管理の優位性
他の従量課金制ツールと比較し、Cursorは固定料金制であるため予算超過のリスクがなく、安心して検証・導入できる点を強調しました。
セキュリティの担保
Businessプランの「プライバシーモード強制機能」により、企業として必要なガバナンスを確保できることを説明。また、事前に「リスクの相談窓口のレビュー」を完了していることも伝え、手続き上の正当性を示しました。
活用方法
- 開発作業
- ドキュメント作成
よく使う機能
- MCP
ツールの良い点
- 予測可能な固定料金制
- 明確な投資対効果(ROI)
- シームレスなコンテキスト連携
- 中央集権的なプライバシー管理
- 課金の一元管理
ツールの課題点
Cursor特有のものではないですが、コンテキストが不足すると良い結果が得られないないので、ドキュメンテーションの文化が無いとROIが合わないこともあると思います。
ツールを検討されている方へ
ミニマムに検証をすれば、ROIを証明しやすいと思います。人によって利用頻度が変わると思うので、適宜プランを見直せると良いでしょう。Ubieでは一部のヘビーユーザー限定で従量課金モードを許可など、利用実態に応じた棚卸しをしています。
Ubie株式会社 / guchey
メンバー / フルスタックエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
新卒でSIerに入社。その後、toB向けSaaSの入社しSaaSの立ち上げに従事。2021年にUbie入社。現在はtoCのグロースチームにて、分析、マーケティング、プロダクト開発、運用と一気通貫で担当。
よく見られているレビュー
Ubie株式会社 / guchey
メンバー / フルスタックエンジニア / 従業員規模: 101名〜300名 / エンジニア組織: 51名〜100名
新卒でSIerに入社。その後、toB向け...
レビューしているツール
目次
- 導入の背景・解決したかった問題
- 活用方法