AIコーディングツール導入のリアル ~意思決定を後押しし、開発を加速させるための7社の実践知~
昨今のAIコーディングツールは日々新しいものが更新され、情報に満ち溢れています。ただ、導入率でいえば、まだまだ一部の企業に限られているのが現状です 。
本記事では、AIコーディングツールの機能比較を行った上で、導入している企業・事業を対象に「導入における課題をどのように解決したのか」「意思決定におけるTips」さらには「そのツールを導入した決め手」を伺いました。少しでもツール導入における意思決定の参考になれば幸いです。
※ご紹介はツール名のアルファベット順となっております
ツール紹介
本特集で取り上げるAIコ―ディングツールについて、ご紹介。(※2025/6現在)
- Cline : Plan/Actモードを備えた自律型エージェント。IDE内でファイル操作やターミナルコマンドを自動化。
- Claude Code : ターミナル常駐型AI。自然言語でコード編集・テスト・Git操作まで実行。IDEプラグインあり。
- Codex : ChatGPT内のクラウドAIエージェント。隔離環境で並列タスクとPR提案を自動化。
- Cursor : VS Code派生のAI IDE。チャットとインライン補完で複数ファイルを一括生成・編集。
- GiHub Copilot : AIペアプログラマ。補完・チャット・PR生成で開発フロー全体を支援。
- Jules : クラウドVM上でリポジトリを検証しPRを自動生成する非同期エージェント。
- Windsurf : コード補完・チャット・自然言語操作・エージェント連携を通じて、開発全体をAIで支援する統合ツール。
7つのAIコーディングツールの比較表
ツール別導入事例のご紹介
Cline / KDDIアジャイル開発センター株式会社
私たちKDDIアジャイル開発センター(KAG)はKDDIの一部署として2013年よりアジャイル開発を行い、2022年にグループ会社として独立しました。10年以上"アジャイル開発"に徹底的にこだわり続けてきたDX専業の組織です。
DXの加速が求められる時代において、我々はアジャイル開発こそが最適解であると強く信じ、デザイン思考も併用したリーンスタートアップ型の開発でグループ企業のサービス開発や、法人企業、地方自治体との共創サービスの実現にも取り組んでいます。
◆導入時の課題と解決策
導入当時(2025年3〜4月頃)は既に全社的にGitHub Copilotを導入していましたが、Agent機能はまだ発展途上でした。そこで、さらなる生産性向上を目指し、より対話的な開発体験が可能な他のAIコーディングツールの可能性を探るべく「Cline」の社内トライアルを企画・実施しました。
知見共有と活用文化の醸成
ツールの導入効果を最大化するには、個々のエンジニアが試すだけでなく、組織全体で知見を共有し、活用ノウハウを蓄積することが必要と考えています。私たちは、トライアル参加者が得た学びや発見を可視化・共有するための取り組みを行いました。具体的には、各メンバーが実際の活用事例をテキストで蓄積するようにした上で、毎週開催される社内勉強会(OST:Open Space Technology)の中で本トライアルに関する議題を設けて、成功体験や課題、効果的な使い方などを議論できる場を定期的に提供しました。これにより、実践的な知識が組織内に広まり、合わせて生成AI活用の文化醸成を推進できました。利用状況管理
トライアルの目的として、生成AIコーディングツールのコスト感を獲得していくという点もあったため、コストの可視化は重視していました。AWS BedrockのApplication Inference Profileを使用し、ユーザーごとの利用料を日時で確認、通知する仕組みを作成しました。また、このモニタ結果は、コスト管理だけではなく、沢山使ったメンバーに活用内容をヒアリングする用途でも活用できました。
◆意思決定のためのTips
Clineのように、利用した分だけ費用が発生する従量課金制のツールは、導入にあたって正確な費用を見積もることが難しく、稟議のハードルとなりがちです。 私たちはこの課題に対し、二段階のアプローチで臨みました。
まず、「コスト感の把握」を目的とした数名規模のパイロット利用を短期・少額で実施。これにより、「どのような作業に、どれくらいのコストがかかるのか」という具体的なデータを収集しました。
そして、その実績データを基に、より現実的な利用シナリオに基づいた費用対効果を算出して本申請を行いました。スモールスタートで具体的な実績と見通しを作ることが、不確実性の高いツールの導入において、関係者の理解と納得を得るための助けとなりました。
◆なぜそのツールを選定したのか
私たちが事業の核とするのは、お客様と一体となってサービスを開発する「共創」です。このスタイルでは、開発に利用するツールやサービス、特にセキュリティに関わる部分は、お客様と合意形成をしながら進める必要があります。
Clineを選定した最大の理由は、特定のAIモデルに縛られず、AWS Bedrockのような大手クラウドプロバイダーが提供するAPIに接続できる柔軟性にありました。
この特徴により、例えば「お客様が契約しているAWSアカウント内のBedrockサービスを利用する」といった構成が可能になります。つまり生成AIの利用も含めた開発環境全体を、お客様自身がセキュリティポリシーに基づきコントロールできることになります。
新たなサービス利用に伴うセキュリティ検討の負荷を大幅に下げ、迅速にAI活用のメリットをお客様に提供できる、という点をClineの優位性と捉えてトライアルの対象としました。
◆ご執筆者のご情報
- お名前: よこせ
Claude Code / 株式会社LayerX
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。
法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル(LLM)関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。
◆導入時の課題と解決策
LayerXではClaude Codeを本格導入する以前、エンジニアがそれぞれCursor、Cline、Roo Code、GitHub Copilotなど多様なツールを利用していました。この状況からClaude Codeが全社的な支持を得るに至った背景には、明確な技術的優位性と、それをいち早く見抜いた現場の動きがありました。
LayerXが全社的にAIコーディングの活用を推進する中で、特にモノレポ環境で開発を進めるがゆえの、いくつかの壁に直面していました。
まず、開発チームごとに技術スタックや文化が異なるため、AIに与えたいコーディングルールが開発者によって異なってしまうという問題がありました。また、エンジニアが常にリポジトリのルートディレクトリから作業を開始するとは限らず、特定のサービスのディレクトリから開いた場合に、AIが共通ルールを認識できないという状況も発生していました。
これらの課題に対しては、ルール適用を補助するツールを自社で開発し、配布することで一定解決することができました。
しかし、より根深い問題が残されていました。それは、400万行を超える巨大なコードベースに起因する「AIに与えるコンテキストが大きくなりすぎる」という課題です 。
少し複雑な実装をさせようとすると、参照するファイルが多く、すぐにAIのコンテキストウィンドウが埋まってしまう。そもそも参照すべきファイルが多すぎて、AIが最適な情報にたどり着けない。
結果として、AIに与えるコンテキストが大きくなると精度が著しく落ち、期待とは異なる挙動をするようになります。この問題に対して、各自で工夫を凝らしていましたが、なかなか有効な解決策を見いだせない状況が続いていました。
◆意思決定のためのTips
LayerXでは、個別のツール導入のたびに各所との調整が必要な稟議を繰り返すのではなく、新しいAIツールを迅速かつ安全に試すための仕組みを事前に整備しています。
- 「AIトライアル予算」で、試行のスピードを上げる
まず、既存の部門予算とは別に、機動的に使える「AIトライアル予算」という専用枠を確保しています。これは、有望なAIツールを迅速に試し、短期間で価値を検証することを目的としています。この予算枠があることで、期初の計画にないツールであっても、通常の予算申請プロセスを経ずにスピーディーな導入判断が可能になります。 - バクラクビジネスカードで、コスト管理を徹底する
新しいAIツールには、企業向けの支払い・アカウント管理機能が未実装のケースも少なくありません。そこで、自社サービスである「バクラクビジネスカード」を活用し、統制の取れた支払い体制を構築しています。サービスごとや個人ごとに利用上限額を設定したバーチャルクレジットカードを発行し、経理部門が支払いを一元管理できるようにすることで、統制の取れないコストの増大を防ぎ、ガバナンスを効かせています。 - 事前定義された規定で、セキュリティリスクを低減する
AIツール特有のリスクに対応するため、「データ保護レベルに応じた利用制限」や「モデル学習への情報流出を防ぐ設定管理」といった運用ルールを事前に明確化しています。新しいツールを検討する際は、このルールに沿ってセキュリティチームが効率よくリスクを評価できるため、安全性を担保しながらも導入までの時間を短縮できます。
これら「予算」「コスト管理」「セキュリティ」の仕組みをあらかじめ整えておくことが、結果的に稟議をスムーズに突破させる鍵となっています。
◆なぜそのツールを選定したのか
そこに登場したのがClaude Codeです。
このツールはRAGに頼るのではなく、高速grepツールであるripgrepを内蔵し、粘り強くリポジトリ内を検索して関連性の高いファイルや実装にたどり着くという、異なるアプローチを取っています。このアプローチが私たちの巨大なモノレポ環境に驚くほど適合し、「恐ろしいくらい上手く動いている」と感じるほどの成果を出したのです。
さらに、開発者体験の面でも決定的な違いがありました。これまでRoo Codeなどでは、意図した出力を得るためにrulesファイルでAIの振る舞いを細かく定義する工夫が必要でした。しかしClaude Codeは、こちらがルールを細かく整備せずとも、曖昧な指示から意図を汲み取り、期待値の80〜90%ほどの精度で実装を完了させてしまう能力を持っていました。
この性能の高さは、これまでのAI Coding Agentより大きな熱狂をもってエンジニアたちに受け入れられました。
現場のエンジニアとCTOがその価値をいち早く発見し、トップダウンの迅速な意思決定によって希望者への配布が開始される。このサイクルが回り、現在ではLayerXのエンジニアリングに不可欠な存在となっています。
Cursor / 株式会社エブリー
エブリーでは、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも」をパーパスに掲げ、レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」/小売DXプロダクト「retailHUB」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ビジネスパーソン向け動画メディア「TIMELINE」など、人々のライフスタイルを豊かにするサービスを複数展開しています。
AIファーストカンパニーを掲げ、社内業務の効率化や開発におけるAI活用のみならず、料理アシスタントである「デリッシュAI」をはじめ、様々なプロダクトでのAI活用を進めています。
◆導入時の課題と解決策
もともと生成AIは社内で活用していたため、大きな課題はなかった。 最大の課題はアカウント管理とコストコントロール。特にコストを気にせず使っていただけるような環境を提供したかった。
◆意思決定のためのTips
費用対効果はまずトライアルで検証。厳密に費用対効果を追いすぎない。 代表や他部署への説明では、Cursorの話だけではなくAIの理解度を高めるために全役員に対して何度かプレゼン・ディスカッションを実施。その中でAI活用が大切であること、特にエンジニアではそれが実用可能なフェーズまで到達していることを理解してもらった。 足元の生産性改善は前提としつつも、未来へのベットとして認識してもらう。
◆なぜそのツールを選定したのか
社内の大半のエンジニアが利用していたIDEがVSCodeだったため、親和性を重視。 Cursorの他、ClineやRoo Code, Windsurfなども検討したが、Cursorが最も良いと判断。 特に 定額プランがあり、使う側がコストを気にせず使うことが可能である点を考え、Cursorを選定。
◆ツールの特性と開発プロセスへの貢献
Cursorに限らず、AI Codingを進める上で「暗黙知になっていたコンテキストをいかにAIに伝えるか」が重要。 それに気づいたチームからドキュメンテーションやオンボーディングの改善が進行中。
弊社では開発生産性10倍を目標に、コーディングアシストだけでなく、要件定義・仕様策定も含めた新しいフロー整備を推進。
◆ご執筆者のご情報
- お名前: 今井啓介
- 役職: CTO
- 所属: 開発本部
- X(旧Twitter)アカウント名: @imakei_
Cursor / 株式会社キカガク
株式会社キカガクは「あるべき教育で人の力を解放する」をミッションとして掲げ、教育を軸として人材領域で企業の DX を支援しています。主なプロダクトとして企業の DX 人材育成支援サービス「キカガク for Business」、A I などの最新技術を e ラーニングで学べる「キカガクラーニング」を提供しています。
◆導入時の課題と解決策
Cursor 導入においては「ツール選定(機能比較)」が大きな課題でした。検討当時(2025/1 - 2025/3)は AI IDE の進化の全盛期で、毎週のように各 IDE に新機能が追加されていました。※ Windsurf, Cline など
そのため「機能」を重視するだけでは意思決定のタイミング次第で優劣が変わってしまう状況でツールの選定が困難な状況でした。
導入までに行った取り組みとしては以下の2つです。
- Cursor を経費申請可能にしてより多くの開発者の声を集める
- Cursor 活用の勉強会(布教会)の実施
上記の取り組みを進める中で、現場からも十分に費用対効果を感じられるという意見が多く、 CTO の一声で導入が決まりました。
※ 取り組み自体も導入にプラス要素となりましたが、それ以上に弊社が AI 活用において風通しの良い環境であったので意思決定がスムーズに進んだという点も大きかったです。
◆なぜそのツールを選定したのか
Cursor の決め手となったポイントは、機能面ももちろんですが重視した観点は「流行」と「将来性」です。
※ 機能に関しては先述した通り状況の入れ替わりが激しいので、機能面以外の観点で意思決定をする必要があった
- 流行
- ブログ等で既に Cursor の導入事例が多数上がっていた
- 真似をできる事例も多く、キャッチアップ&活用までのコストが低いと感じた - 将来性
- AI IDE の先駆者として機能追加に関してのスピード/内容は信頼を持てる実績があった
- そのため、数ヶ月先においてもトップランナーであり続けているであろう信頼感を持てた
◆ご執筆者のご情報
- お名前: 石橋鉄朗
- X(旧Twitter)アカウント名: @tetsuro_b
GitHub Copilot / 株式会社dely
2014年創業。主力サービスである国内No.1レシピ動画「クラシル」と、お買い物サポートアプリ「クラシルリワード」の合計月間利用者数は4,100万人を超えています。
「クラシル」ブランドを軸に、ユーザーの暮らしに寄り添う複数のサービスを展開。近年は、これらの強固なサービス基盤を活用し、小売・流通業界に向けたDX支援サービスを強化しています。2024年12月に東証グロース市場へ上場し、2025年10月には社名を「クラシル」へ変更予定です。
◆導入時の課題と解決策
弊社では2023年2月にCopilotを導入しました。AIに限らず新規ツールを導入する際は必ず社内で法務レビューを実施していますが、Copilotの導入においては特に問題や懸念事項は発生しませんでした。
◆意思決定のためのTips
AI関連ツールの導入にあたっては、事前にROIを厳密に算出するのではなく、まずは少人数で迅速にPOCを開始し、利用状況や効果を可視化した上で全社展開の判断材料としています。POC得られた実績を根拠に、意思決定を行いながら積極的に生産性向上に資するツールなどの導入を推進しています。
◆なぜそのツールを選定したのか
弊社ではCopilot以外にもCursor、Claude Code、Devinなど多数のAIコーディングツールを積極的に導入していますが、Copilotを選定した最大の理由は、コーディング支援に留まらない幅広い機能と高い費用対効果にあります。
VSCode上でのコーディング支援だけでなく、Copilot ReviewによるPRレビューの効率化や、GitHub Modelsを活用することでGitHub Actionsへ簡単にLLMを組み込むことなども可能です。
競争が激しいAIコーディングツール市場において、これらの機能を単一のプラットフォームで網羅的に提供している点が強みであり、他ツールと併用してでもCopilotのいずれかの機能を日々利用することで高い費用対効果を実現していると判断しました。
◆ご執筆者のご情報
- お名前: 坂口 楽
- 役職: SRE
- X(旧Twitter)アカウント名: @rakutek
GitHub Copilot / 株式会社L&E Group
株式会社L&E Groupは「インターネットで 商いつくる 商いつなぐ 商いひろげる」をビジョンとして掲げ、成果報酬型広告のマッチングプラットフォーム『Link-AG』を中心に、様々なデジタルマーケティング事業に取り組んでいます。
◆導入時の課題と解決策
導入時に苦労したことや課題は特にありませんでした。普段使用している GitHub や VSCode の設定を少し変更したり、拡張機能をインストールしたりするだけで済んだため、導入は非常にスムーズでした。
新しい機能がリリースされた際は、参考にできる記事などが少ないため、使いこなせるようになるまで少し時間がかかることがあります。
◆意思決定のためのTips
弊社は、便利なツールや新しいツールに関しては、積極的に導入するカルチャーなので、GitHub Copilot の導入にあたって特別な稟議は不要でした。
もし稟議が必要な場合、以下の点を訴求するといいかもしれません。
選べる2つのプラン:GitHub Copilot の法人向けには、Business プラン($19/ユーザー・月)と Enterprise プラン($39/ユーザー・月)の2つがあり、使用したい回数や求める機能に応じて、プランを選択することができる。
導入の手軽さ:普段から GitHub や VSCode を使用している場合は、設定を少し変更したり、拡張機能をインストールしたりするだけで導入が済む。
豊富な機能:コード補完、コードレビュー、エージェントといった豊富な機能が備わっている。また、頻繁にアップデートされているので、さらなる性能の向上や、新機能の追加が期待できる。
◆なぜそのツールを選定したのか
会社として GitHub Copilot を導入したのは2023年4月頃です。コード補完が便利だということで導入しました。実際に使ってみると非常に便利で、他の AI ツールも多くありますが、以来ずっと GitHub Copilot を使い続けています。今ではコード補完以外にも便利な機能が多く、手放せないツールとなっています。
◆ご執筆者のご情報
- お名前: 大隈 亮哉
- 所属: プロダクト開発部
- X(旧Twitter)アカウント名: @kumaryoya
Windsurf / エムスリー株式会社
30以上のWebプロダクトを開発、100以上の医療事業を展開しています。国内の9割以上の医師が会員となるプラットフォーム『m3.com』、日本導入数No. 1の電子カルテ『デジカル』、病院の待ち時間を0にする医療DXアプリ『デジスマ』、会員数500万人超の医師Q&Aサービス『AskDoctors』など、エンジニアリングが中心となるtoB/toCプロダクトも多く開発、運用しています。
◆導入時の課題と解決策
エムスリーは非常にコンパクトな組織で、全社員650名、エンジニア100名程で事業をつくっています。東証プライム上場企業でWeb開発をする企業群の中でもエンジニアの数は比較的多くなく、1チーム平均5名程です。その前提において、1人あたりの開発生産性が向上することは多大なインパクトに繋がると認識しています。ROIを最大化すべく、常に開発体験の改善に取り組んでいます。
また、140社を超えるグループ会社に対しての技術的支援にも取り組んでいます。1社のプロダクト改善を1~2名で一気に押し進める事もある中で、開発の相棒と呼べる存在が必要とされていました。
◆意思決定のためのTips
エムスリーでは、AIコーディングツールを段階的に導入しています。
2023年のグループ会社を含めたChatGPTのチャット利用から始まり、元々活用していたGitHubが提供するCopilotを試験導入、いくつかのチームで事前検証しています。
その中で、いくつか課題のあったプロジェクトの実際の改善体験を積み重ねました。遅延のあった大規模プロジェクトを10名弱でAIコーディングツールを使って完遂させるなどの実績に加え、生産性が上がるパターンや条件、環境を検証し、AI活用度のレベル表なども社内で作成して進めました。
その後、AWS、GCPを元々活用していた事もあり、AWS BedrockやGemini導入からAIコーディングツールの本格的な全社導入が始まりました。実際にこれまでの体験で生成AIツールの実績があったため比較的スムーズに進める事ができました。セキュリティ面もAWS、GCPのサポートの方々と話しながら進める事ができ、どういったシーンで使ってよいかなどの社内定義も作りやすく良かったかなと思います。
会員限定コンテンツ無料登録してアーキテクチャを見る
現在では、様々なAIコーディングツールを導入し、適材適所に活用しています。各ツールのセキュリティや契約面を考慮し、OSSの場合は内部実装を読むなどしながら導入を進めています。CTO、VPoE共に機械学習分野出身で、生成AI並びにAI技術に精通している点も寄与していると思います。
◆なぜそのツールを選定したのか
エムスリーは、もとより技術選定を現場に一任しています。適材適所な技術選定眼を磨き、より良いプロダクトを世の中に届けるためです。
会員限定コンテンツ無料登録してアーキテクチャを見る
故に、メジャーなAIコーディングツールはもちろんJetBrains AIやwindsurf、Avante.nvimなども利用者がいます。エムスリーでは、Kotlinを筆頭にAppやバックエンドでのJVM系言語も活用しています。こういった言語はIDEとの相性が良く、エンジニアもIDEに慣れているためツール導入の際の障壁が極端に小さくなります。
私もですが熱心にvimを使っている人も居ますので、手に馴染み、技術に馴染むツールを使ってもらえるよう、セキュリティや活用要件の整備を日々行っています。
◆ご執筆者のご情報
- お名前: 河合
- 役職: VPoE
- X(旧Twitter)アカウント名: @vaaaaanquish







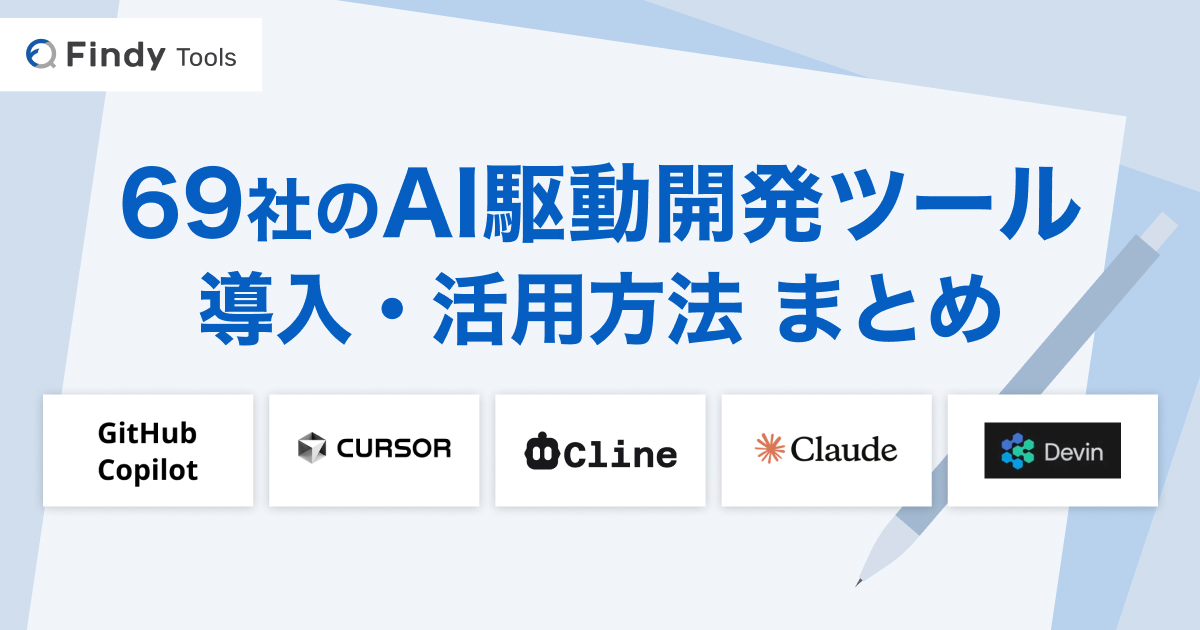
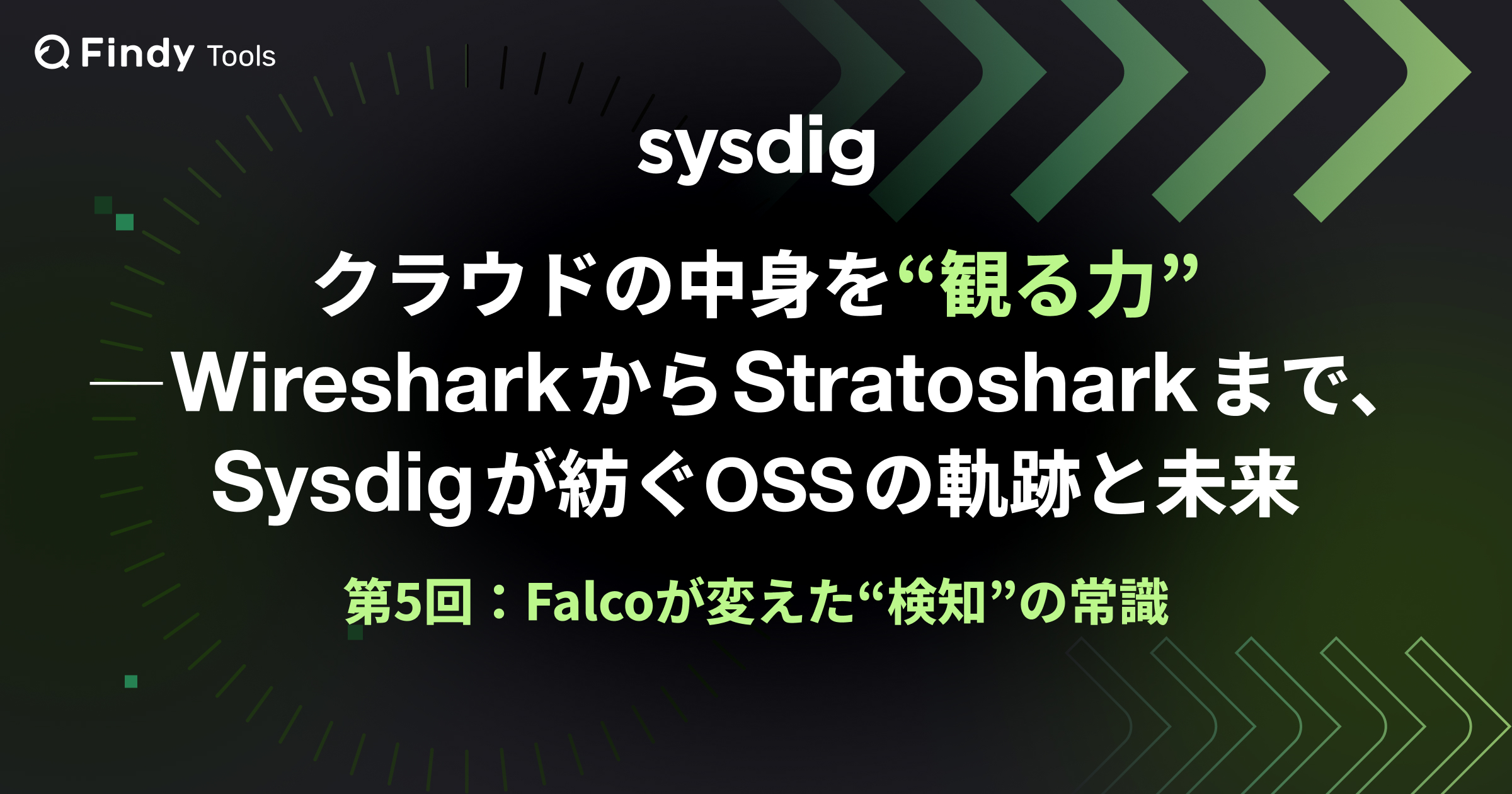








.png)


