【内製開発Summit 2025】現代的な企業ITインフラ基盤の作り方
2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit2025」が開催されました。本カンファレンスは、野村コンファレンスプラザ日本橋(東京)にて実施され、一部のセッションはオンライン配信も行われました。
本記事では、オンラインでも配信されたセッションのうち、一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会の岡村慎太郎さんと、株式会社クラウドネイティブの代表取締役社長である齊藤愼仁さんによるセッション「現代的な企業ITインフラ基盤の作り方」の内容をお届けします。
あらゆるシーンでデジタル化が進んでいる現代。クラウド環境での運用管理が複雑化し、サイバー攻撃の脅威も高まっているなかで、ITインフラ基盤はどのようにして構築していくべきなのか?内製開発のメリットとは何なのか?情報システムのスペシャリストに話を伺いました。
■プロフィール
岡村 慎太郎(おかむら しんたろう)/ (@okash1n)
一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会
代表理事
香川大学医学部医学科中退後、Sansan株式会社、アソビュー株式会社、株式会社スタディストなどでインフラエンジニアやSRE、情シスに従事。スタディストでの業務の傍ら、2021年、創業35年の自家焙煎珈琲豆販売業を営む有限会社脇屋の代表取締役に就任し、オンラインショップの立ち上げやDXに取り組む。2022年、一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会を立ち上げ代表理事に就任し、情シスSlackやBTCONJPの管理・運営に携わり、現在もビジネステクノロジーの普及に取りくんでいる。
齊藤 愼仁(さいとう しんじ) / (@sudachikawaii)
株式会社クラウドネイティブ
代表取締役社長
データセンターや科学技術計算向けの高密度計算機の企画・設計に参画し、GPUやコプロセッサを活用した計算機の設計経験を有する。国内最大級のAWSインテグレーターで情報システム、ネットワーク、セキュリティの3チームを統括。2017年に情報システムコンサルティングを主軸とする株式会社クラウドネイティブを創業し、社内ITにおけるゼロトラストアーキテクチャの実装と運用を民間企業から行政機関まで幅広く支援。2022年から文部科学省最高情報セキュリティアドバイザーに就任。
ITインフラ基盤に必要となるのは弾力性と拡張性
──本日のファシリテーターを務めるファインディの高島と申します。このセッションでは「現代的な企業ITインフラ基盤の作り方」と題し、4つのテーマについてパネルディスカッション形式でお話を伺います。最初に、本日ご登壇いただく岡村様、齊藤様、自己紹介をお願いいたします。
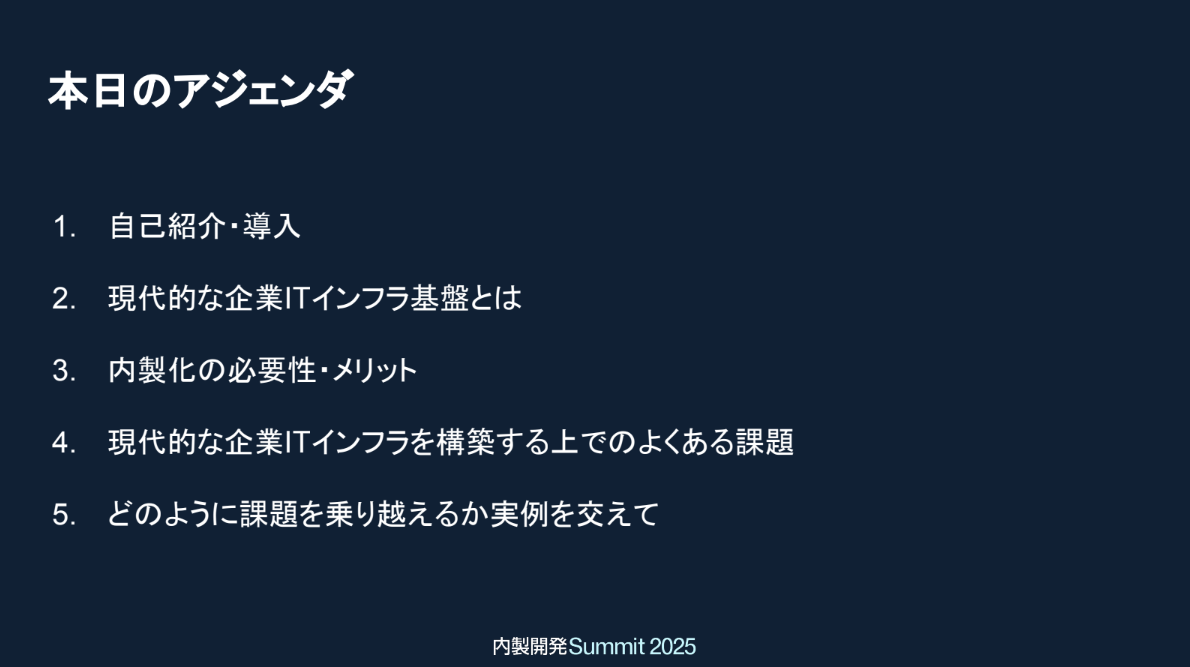
岡村:岡村慎太郎と申します。私はSIerのようなところで消費者金融のシステムなどを担当したあと、Sansan株式会社で情シスをしていました。その後は開発に軸足を移してSREとして活動していて、最近はまた情シスに戻ってきました。また、2022年より情シスに関するコミュニティを運営しています。本日はよろしくお願いいたします。
齊藤:情報システム部門に特化したコンサルティングサービスを提供している株式会社クラウドネイティブの齊藤です。2022年から文部科学省の最高情報セキュリティアドバイザーとしても活動しています。本日はよろしくお願いいたします。
──ありがとうございます。それでは早速一つ目のテーマ「現代的な企業ITインフラ基盤とは」について、お二人のお考えをお聞かせください。
岡村:まず思い浮かぶのは、柔軟性と拡張性ですよね。ビジネスニーズに応じて、何かあれば業務やビジネスのプロセスをITによって効率化していく。そういったことが素早く出来るだけでなく、情報を守るセキュアさを兼ね備えていて、且つ柔軟に変えていける、というのが現代的なITインフラ基盤だと言えるのではないかと。概論的ではありますが、そう考えています。
齊藤:岡村さんと同意見ですね。補足するならば、何でもかんでもクラウドにすればいい、内製開発をしたらいい、という話ではないと思います。会社の状況や課題をクリアにしなければ「最適なITインフラとは?」という問いの答えは出てこないと思うんですよ。ちなみに、来場者の皆様はどういった方が多いのでしょうか?
──今日ご参加いただいているのは1000名以上の大企業の方が多く、その中の2割ほどが内製開発をされています。そのほかの2割は一部だけ内製開発をされていて、残りの6割はこれから内製化を目指されているという状況です。
齊藤:なるほど。それで言うと、コロナ禍でインフラの拡張がリモートワークに追いつかない、というのはよく聞きましたね。現在では、逆にリモートワークを辞める流れになってきていますけど。「出社最高!」みたいな。
岡村:マネジメント観点でリモートワークを廃止、もしくは減らすケースは多いようですね。
齊藤:そうなると、ITのあり方って変わってきますよね。「コロナ禍でインフラを整えたのに、もう使わない」なんてこともあり得るわけで。状況によって必要なものが変わっていくという前提で考えると、柔軟性というよりは弾力性が必要なのではないかと思います。インフラに弾力性を持たせるためには、どうすればいいのか。岡村さんはどう思われますか?
岡村:弾力性がないというのは、ニーズが出てきたときに対応できない、もしくは対応できたとしても時間がかかってしまう状態のことだと思っています。弾力性を持たせるためには、何が起きても対応できるように整えておく、進む可能性のある道を経営陣と常にすり合わせておくことが重要なのかなと。
要は「ビジネスニーズを把握できているか」「それに沿った対応ができるように準備できているか」という観点が必要なのだと思います。
内製化にトライする上で重要なのは「開発の過程を知ること」
──ここからは「内製化の必要性・メリット」をテーマにお話しを伺いたいと思います。お二方、よろしくお願いいたします。
齊藤:例えば、ネットワークやVPNにしても、拡張もしくは縮退する必要が出てきたとき、それら全てが外注に握られているケースがあったとします。3ヶ月の納期で報酬は1000万円、変更する箇所は“Wordでぺら1”みたいな。そういった話を聞くと「やられちゃってるな」と思います。
岡村:そういうケースは多いですね。
最近だと、ChatGPTをそのまま使うのではなく社内AIを構築しましょう、といった外注の案件もたくさんあると思います。ただ、カスタマイズしようと思ったら、追加開発が必要になってくると。世の中にはパッと利用できるものがあるのに、外注だと類似機能が開発できないなど、そういった状況に陥っているケースは少なくありません。
齊藤:内製化を真っ向から否定してくるクラスターもいますよね。一部の業務プロセスをクラウドサービスとして提供するBPaaSに携わっている方々は「外に投げなさい」「餅は餅屋。プロに仕事を任せた方が仕上がりもいいです」という言い方をされます。ただ、開発に時間がかかりすぎる、内容に対して報酬が高すぎるといったケースもありますしね。
例えば、家具が欲しいとなった時、自分で素材を調べてイチから手作りする人は少ないでしょう。
──私はたまに作ります(笑)。
齊藤:でも、それってDIYの範囲であって、頻繁に作るものではないじゃないですか。問題は頻度なんですよ。あとは業務でやるかどうか。つまり、運用の効率やクオリティの担保が、組織的に必要だという話なんです。
先ほど岡村さんがお話されていた社内AIの外注事例は、頻度の話なんですよね。「どの程度の頻度で変更が発生するのか」「柔軟性が必要な部分なのか」というところを見極められないのであれば、外注か内製かの判断はできないと思います。
もっと言うと、一番良くないのは「わからないから外注しよう」というケースです。なぜならば、ITを理解していない人は、納品されたものに対する品質の評価ができませんから。お餅ならほとんどの人が味を判断できますが、ITの場合はそうはいきません。プロに丸投げして1年ほどかけて予算を1億円かけたものができたときに、その品質が評価できないのは会社としてまずいでしょう。
岡村:納品されるならまだマシ、という感じですよね。
齊藤:そうそう。だから最初から全部を作るのではなく、伴走しながら一緒に理解を深めてくれるパートナーを探さないと、自分たちの内製化はちょっと難しいのかなと。
──確かに、おっしゃる通りですね。
岡村:結局のところ「自分たちはプロではないので」と逃げることはできないんですよね。それに、先ほどもお話ししたように、外注して開発してもらえるならまだマシなんですよ。自分たちが希望する内容を伝えられないケースは結構ありますし、そうなると開発自体も上手く進みませんから。
──確かに、要件定義ができないとなると、開発は進みませんよね。そう考えると、一定レベルでは内製できる方が社内にいた方がいた方がいいと。
齊藤:そうですね。コードが書けるか書けないかっていう極端な話ではなくて、書けなくていいんです。書けなくてもいいんだけど、書ける人たちがどのようなプロセスでモノを仕上げてどうやって評価しているのか、っていう過程を知っておく必要はあると。そういう意味での内製化が大事だよという話ですね。
ITインフラを構築する上での課題は大小さまざま
──続けて「現代的な企業ITインフラを構築する上でのよくある課題」についてお話しを伺います。新しく企業ITインフラを構築するとなったときの課題というと、どのようなものがあるのでしょうか?
齊藤:シチュエーションによりけりだとは思いますけどね。例えば、自社のオンプレミスのデータセンターがたくさんあって、それを縮小するというプロジェクトがあったとします。その場合、移行先の候補に出てくるのは AWS や Azure 、 Oracle などのクラウドサービスでしょう。そうすると、自分たちでは対応できないから「どこのベンダーに依頼すればいいんだろう?」という話が出てきますよね。そこで、先ほどの話に戻るんです。ベンダーをどうやって評価するの?っていう。
あとは、最初からセキュリティを考慮すると考える項目が多すぎてパニックになる、という問題もよく発生していると思います。
──なるほど。岡村様はいかがですか?
岡村:齊藤さんのお話と少し異なるところで言うと、何かを変えていきたいのに社内のセキュリティポリシーとバッティングしてしまってプロジェクトが進まない、というケースは結構あるように思います。
──私もいくつかの企業で同様のケースを聞いたことがあります。あとは一部でWindowsを使っていて、Macを導入したいのだけれどサービスカタログに当てはまらないため導入できない、とか。
齊藤:大手企業あるあるですね。新しいビジネスを始める際に専用のインフラを立ち上げようとしたものの、既存のセキュリティとバッティングしてしまうっていう。その手の解決策として分社化するというのが、“大手のやり方”という感じがしますね。「〇〇デジタル」みたいな名前の会社を作る、とかね。
岡村:ジョイントベンチャーを立ち上げるケースもありますよね。
齊藤:それで、その組織専用のセキュリティ体制をイチから構築し直すっていう。そういうケースは結構ありますよね。
──なるほど。他に何かありますか?
岡村:単純に能力値の問題があり、基盤を作ったのに組織に浸透させられないというのもあります。社内で情報伝達する仕組みがないとか、事業部門が強すぎるとか、理由は色々あると思いますが。
──シンプルに表現すると「会社が情シスの言うことを聞いてくれない」ということですね。
岡村:そうですね。事業部門からの要求ありきで、その場しのぎにいろんなアーキテクチャができてしまっている場合は、そういった問題が発生しやすい気がします。
──昨今は「AI」の話を聞かない日はないように思います。AIを入れるにしても、インフラ観点で検討すべき項目が多いように思いますが、その点はいかがでしょうか?
齊藤:どうなんでしょう。AI自体がクラウドサービスですからね。
岡村:そうですね。ITに乗せる情報はそれぞれに重要性があり、それをうまく活用できて、かつセキュアに保たなければいけません。考えることが多いというのは、AIに限ったことではないと思います。
──なるほど。
齊藤:全く話が変わるのですが、多くの会社に共通しているのは「人が足りていない問題」だと思います。人が足りない、仕事が多すぎる、早く帰りたい、人材が育たない。そういった問題が解決されていないから、新しいことにトライしたいけど既存の業務に振り回されていて何もできない、みたいなシチュエーションは結構あるんじゃないでしょうか。
課題解決の鍵は「現場と経営層のコミュニケーション」
──いろんな課題をお話いただきましたね。それでは次は「どのように課題を乗り越えるか実例を交えて」をテーマにお話いただきます。具体的な事例があると嬉しいのですが、いかがでしょうか?
岡村:事例と言えるのかはわかりませんが、私が講演などに登壇した際は「メンバーは会社がどこに進んでいこうとしているのか知りましょう」「経営陣側はそれを広めましょう。周知させるための場を持ちましょう」と伝えるようにしています。
齊藤:リーダーシップメントは絶対必要ですね。Cクラスの方、もしくは情報システムやセキュリティ部門長が「我が社はこういうプロセスで進みます」とはっきりと伝えなくてはいけない。その時、内製なのか外注の見直しなのか、具体的なところまでは踏み込まなくてもいいと思います。それよりも、何がしたいのか、どういったプロセスを取っていくのか、方向性を決めることが重要なのかなと。
岡村:よくあるのが「経営陣から急に『コストカットをするから〇〇を止めなさい』って通知がきた」というケースですね。こういった問題が発生するのは、社内のコミュニケーションが不足していることが原因だと思うんです。
──なるほど。普段から「経営陣とメンバーがコミュニケーションする場」を作ることも重要なことの一つなんですね。
齊藤:今日会場に来ているのはエンジニアリングをされている方だと思うので「エンジニアが何をすると評価されるのか」が気になるのではないでしょうか。
それは会社によって違いますし「我々の会社ではこういう人たちが評価されますよ」というのを、四半期レベルで見せていかないと、なかなか難しいのかなと。1年ごとに発表するとかだと、ちょっと長すぎますよね。テクノロジーの感覚からすると、1年はかなり長いですから。
──AIだと、1ヶ月で違うモデルが出てくることもありますしね。
齊藤:現場にいて「評価軸がわからない」という問題があるのであれば、経営層に対してそういった情報の開示、もしくは方向性を示してくれるようにアプローチしてみることも必要だと思います。
──アプローチをするにしても、経営層のなかにITがわかる方がいないと、議論が成立しないのではないかという心配もあるのではないかと思いました。
岡村:個人的には、経営層がエンジニアレベルでITを理解していないといけない、なんてことはないと思います。それにとどまらないこともあるかもしれませんが、ITはあくまで手段です。
ビジネス的にどういうことをしたいのか、コストのことなど、共通言語で話すようにすればお互いに理解できるのではないかと思います。
齊藤:そうですね。上司がITをわかっていないって、実はそんなに問題じゃないと思います。それよりも、上司が企業活動や自分たちの部下のマネジメントも含めて「相手を知る」ことを必要としているかどうかが問題なんです。
必要ないのであれば、岡村さんがお話されていたように共通言語で話すだけで問題ない。そもそも、必要であれば、ITについて勉強するとか何かしらのアプローチをしているはずですから。必要なのに行動しないような上司なのであれば、それはデコピンするしかありませんけど(笑)。
例えば、弊社のクライアントには前向きな方がとても多いんです。経営層がITのことをわかっていなくても、実は社長がセキュリティ系のセミナーに行っているとか、部長が現場の人とコミュニケーションを取りながら勉強しているとか。わからなくても、理解しようと頑張っている方が多いんですよ。そういった姿勢は部下にも伝わりますし、経営層が前向きかどうか、というのはとても大事なポイントだと思います。
──メンバーから何かを提案するときには、どうやって伝えると有効的だと思いますか?
岡村:「こうすると儲かりますよ」みたいな話は、通じやすいのではないかと思います。
齊藤:そうですね。「自分たちの作業を自動化して簡単にしました」みたいな話って、実は結構小粒で。それによって全社的にどれだけ労働コストを削減できるか、みたいなところまで広げないと伝わらないと思います。
──コストなどのベネフィットにつなげていくことがポイントということですね。それは確かにおっしゃる通りで、風土の変革にも繋がるような気はします。
齊藤:全てをお金の話につなげるべき、とは思わないんですけどね。会社によって企業文化はそれぞれですし、それを良くしていくためのアプローチも必要だと思います。
──新たな取り組みをしたいと思ったとき、セキュリティも欠かせなくなってきていると思います。何をどこまでやっていくのか、が課題だと思うのですが、そこはどのように乗り越えていくべきなのでしょうか?
岡村:セキュリティの領域には「これを絶対やらなきゃいけない」というものは存在していなくて。扱う情報の内容や流出した場合のリスク、そのリスクが発生する可能性や頻度などについて分析した上で、事業インパクトのあるところから対応するというのが基本の考え方です。
何から取り掛かるのか、その順番を明らかにするのは最初にするべきことで、これはビジネス的に一番重要な部分についての話でもあると。そう考えると、やはり経営層と話して決めていかなくてはいけないと思います。
──セキュリティ対策をするにしても、ITに投資をしていくにしても「どのようなベネフィットがあるのか」「どこに情報があってどんなものを守っていくのか、そのために何をすべきか」を考えていかなければいけないということですね。
岡村:そうですね。
齊藤:どの部分の開発で、どれだけの規模感で、開発したものにどんな情報が入っているのかを評価する、っていうのが最初にやることなんですけど、それって数をこなさないとわからないんですよね。だから、数をこなして自分に叩きつけていくしかない。数をこなしていくと、何かを作ろうと思ったときや何かの情報を見たときに「どんなセキュリティ評価をしないといけないか」が頭の中に出てくるようになります。
──数をこなすための始めの一歩でいうと、何からがいいと思いますか?
齊藤:“自社のセキュリティ基準の見直し”がいいと思います。そのほか一番簡単なのは、他社の失敗事例を見ることですね。
──最近は分析結果などの詳細な情報が公開されていますものね。
齊藤:そうそう。あれってよくできているので、見ていると勉強になりますよ。
自社にとって必要なものを見極めつつ、内製開発にトライしていく
──最後に、ご参加いただいた会場の皆様に向けて、メッセージをお願いいたします。
岡村:セキュリティに関して「こうしなきゃいけない」といった話が世の中には蔓延っていると思いますが、そういった情報には騙されないようにしてほしいです。情報を知っておくことはいいことですが、鵜呑みにしすぎないように。自社にとって大事なものが何なのかを考えて、メンバーとコミュニケーションを取りながら事業を進めていただければと思います。
齊藤:内製開発という意味で、iPaaSやZapierを活用している人が増えてきていると思います。それをもっと広げて、自分たちが日々繰り返している業務を改めて評価して、自動化して、圧縮する。そして、自分たちの業務負担を可能な限りコンピュータ側に移動させていくことで、新しいことに挑戦するためのリソースを作っていくことができると思います。それは内製開発のファーストステップでもありますし、ぜひその辺を頑張ってもらえればと思います。
──岡村さん、齊藤さん、本日はお時間をいただきありがとうございました!



.png)





