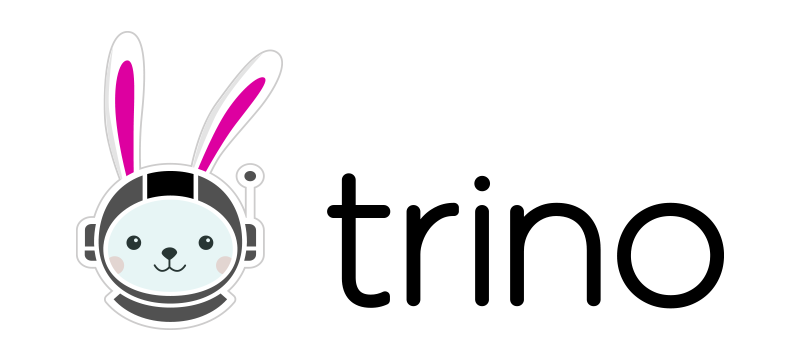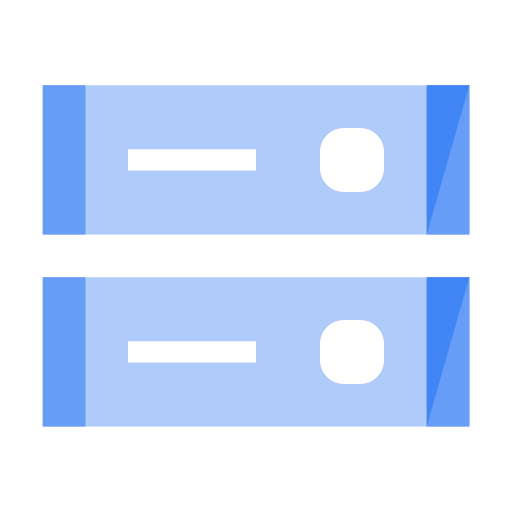データ分析向けデータベースカオスマップ 2025年下期版
膨大なデータが日々生まれる現代、企業の意思決定は「どれだけ迅速かつ正確にデータを活用できるか」にかかっています。
生成AIや高度な分析技術の活用が広がるなか、ベクトル検索やリアルタイム集計など、新しいデータ活用の手法も注目を集めています。
本カオスマップでは、代表的な分析向けデータ基盤ツールを、「DWH」「レイクハウス」「データレイク/補助ツール」「ベクトルDB」「リアルタイム分析DB」「クエリエンジン」といったカテゴリに整理し、それぞれの特徴や選定ポイントを解説します。
※本記事で取り上げるカテゴリには、純粋なデータベース製品に加え、データレイク管理基盤やクエリエンジン、リアルタイム分析基盤なども含まれています。これらは厳密には役割や機能が異なりますが、いずれも「データ分析を支えるストレージ/処理レイヤー」として活用されるケースが多いため、便宜上ひとつのマップに整理しています。
また、分析向けDBには集計系だけでなく、類似検索やAI向け検索などの用途も含まれます。
データ分析向けデータベース全体像
会員限定コンテンツ無料登録してアーキテクチャを見る
掲載しているロゴ・商標等の取り扱いについて問題や懸念がございましたら、下記の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
また、ロゴの掲載をご希望される場合も、お問い合わせいただけますと幸いです。
【お問い合わせ先】
ファインディ株式会社 データ分析向けデータベースカオスマップ制作担当者
findy_tools@findy.co.jp
次のセクションからは各カテゴリの解説や導入時のポイントをご紹介していきます。
DWH
データウェアハウス(DWH)は、複数ソースのデータを統合して分析に最適化した中央リポジトリであり、BIやバッチ/対話的分析の基盤として使われます。近年はストレージとコンピュートの分離、サーバーレス的な運用、そしてデータレイク/レイクハウスとの融合が顕著なトレンドです。
■ このカテゴリのツール例
| Snowflake | Snowflakeはストレージ・コンピュート・サービス層を分離したアーキテクチャで、複数クラウド上で同一プラットフォームを提供する点が特徴です。ワークロードごとに独立した仮想ウェアハウスを割り当てて並行実行性を確保できるため、高い同時実行性が求められる分析・BI環境に向いています。 Snowflakeページはこちら |
|---|---|
| BigQuery | BigQueryは「サーバーレス」なデータウェアハウスで、ユーザー側でインフラ管理を意識せずスケールできる点が大きな特徴です。ストレージとコンピュートを分離した設計により、データの保管とクエリ実行を独立して最適化でき、BigQuery内部のMLやデータフロー、GCPサービスとのシームレス連携が求められるケースで優位になります。 BigQueryページはこちら |
| Amazon Redshift | Redshiftは長年の実績を持つAWSのDWHで、最近はRA3ノード(Redshift Managed Storage)やServerlessのオプションにより、ストレージとコンピュートの分離を取り入れつつAWSサービス群との深い統合を強みにしています。 Amazon Redshiftページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
Azure Synapse Analytics / Oracle Autonomous Data Warehouse / SAP Data Warehouse Cloud / IBM Db2 Warehouse / Teradata / Vertica / EXASOL / Firebolt / Yellowbrick / VMware Greenplum / Actian Vector / Amazon FinSpace / SAP Datasphere / IBM Netezza Performance Server / Oracle Exadata Cloud Service
■ 特徴と役割
- ストレージとコンピュートの分離により、容量増加とクエリ負荷を独立して最適化できる
- 大量データの集計・BI・複雑な分析クエリを効率的に処理するために列指向ストレージとMassively Parallel Processing(MPP)を採用
- 最近はレイクハウスやオープンフォーマットと連携し、リアルタイム/ストリーミングデータやAI用途との融合が進んでいる
■ ツール選定時のポイント
- 費用モデル:ストレージ課金とクエリ/コンピュート課金のバランスを把握し、想定ワークロードでの総TCOを試算する
- 運用モデル:インフラ運用負荷をどこまで許容するか
- クラウドロックインとマルチクラウド:複数クラウドでの可用性やデータ移動戦略が必要か、ベンダ固有機能への依存度を評価する
- データ統合とエコシステム適合性:既存のデータレイク、ETLツール、データカタログ、BIツールとの接続性を検証する
- ワークロード特性:分析の同時ユーザー数やクエリレイテンシ要件に応じて、仮想ウェアハウスの分離やキャッシュ戦略を検討する
レイクハウス
レイクハウスは、データレイクの柔軟性とDWHの信頼性を統合した新しいデータ基盤アーキテクチャです。
分析・機械学習・リアルタイム処理を単一のデータレイヤーで実現することを目的としており、オープンテーブルフォーマットを中心に、クラウドストレージ上に「信頼できる分析層」を直接構築する流れが加速しています。
■ このカテゴリのツール例
| Databricks | Databricksは「Lakehouse Architecture」を提唱した企業で、データエンジニアリング、BI、ML/AIのワークロードを統合的に扱うプラットフォームを提供しています。Delta Lake形式を基盤とし、ACIDトランザクション・スキーマ管理・タイムトラベル機能をサポートします。 Databricksページはこちら |
|---|
💡他にも下記ツールがあります
IBM watsonx.data /
Onehouse
■ 特徴と役割
- 生データの柔軟な蓄積とACID保証・スキーマ管理を同時に実現
- Delta Lake、Iceberg、Hudiなどのテーブルフォーマットにより、複数クエリエンジンやクラウド環境間での可搬性を確保できる
- ETL・特徴量生成・モデル学習・推論を同一基盤上で完結でき、MLOpsの効率化につながる
- リアルタイム/ストリーミング対応等、低レイテンシな分析を実現できる
■ ツール選定時のポイント
- テーブルフォーマットの選定:フォーマット間で互換性・エコシステム対応状況・更新方式が異なる
- クエリエンジンとの統合性:利用中の分析エンジンがどのフォーマットをネイティブサポートしているかを確認
- メタデータ管理の仕組み:メタストアの一元管理やバージョニング機能との統合可否を考慮する
- 運用負荷とガバナンス:オープン基盤は柔軟だが、データ品質保証やスキーマエボリューションの運用ルール設計が不可欠
- ストレージコストと更新頻度:高頻度更新が多い場合、ファイルフラグメンテーションやストレージ最適化の自動化の仕組みが重要
データレイク
データレイクは、構造化・非構造化を問わずあらゆるデータをそのまま蓄積できるストレージ基盤です。
DWHのような事前スキーマ定義を必要とせず、柔軟なスキーマ・オン・リード方式を採用することで、分析・AI活用・アーカイブを横断的に支える基盤として広く利用されています。
■ このカテゴリのツール例
| Amazon S3 | Amazon S3は、クラウドストレージとして最も広く採用されており、ほぼすべてのデータ分析・AIツールのデフォルトストレージとなっています。
堅牢な設計に加え、AWSサービスとの高い統合性が特長。コスト最適化のための階層型ストレージも豊富で、アーカイブからリアルタイム分析まで幅広い用途をカバーします。 Amazon S3ページはこちら |
|---|---|
| Google Cloud Storage | Google Cloud Storage(GCS)は、BigQuery・Vertex AIなどとのシームレスな統合により、機械学習や生成AI基盤としての利用が増加しています。ストレージクラスの柔軟な切り替えにより、アクセス頻度に応じたコスト最適化が容易。 Google Cloud Storageページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
Amazon Simple Storage Service Glacier /
Amazon S3 on Outposts /
Apache Hadoop /
Cloudera /
Azure Data Lake Storage
■ 特徴と役割
- 画像・動画・ログ・センサーなど、多様な形式をそのまま一元保存できる
- データを保存時に構造化せず、利用時にスキーマを定義する柔軟性を持つ(スキーマ・オン・リード)
- DWH、レイクハウス、ベクトルDBなど、上位レイヤーの基盤として機能する
■ ツール選定時のポイント
- 既存クラウド環境との親和性:AWS・Azure・GCPいずれを中心とするかで、ツール連携性が大きく変わる
- セキュリティとガバナンス:IAM連携・暗号化・アクセスログ管理など、組織要件に適合するかを確認
- コスト最適化:アクセス頻度に応じてストレージクラスを使い分ける運用設計が重要
- 分析基盤との連携性:後続で利用するDWHやLakehouseとのデータフォーマット互換を考慮
データレイク 補助ツール
データレイク補助ツールは、レイク上のデータを「使える状態」にするための管理・統合・カタログ機能を提供するツール群です。
単なるファイルストレージでは実現できない、メタデータ管理・アクセス制御・データ品質保証などを担い、レイクの“信頼性”を高める役割を果たします。
■ このカテゴリのツール例
| AWS Lake Formation | S3上のデータを対象に、レイク構築・アクセス制御・メタデータ管理を統合的に実施できるサービスです。Glue Data Catalogと連携し、権限設定やデータパーティションを自動生成。AWS IAMとの統合により、企業全体でのデータ権限管理を簡略化できます。 AWS Lake Formationページはこちら |
|---|---|
| Dataplex | Dataplexは、GCS・BigQuery・外部クラウドのデータを一元的に管理するメタデータ統合基盤です。仮想的な「論理データレイク」を構築し、分散データの統合ビューとポリシー管理を可能にするのが特徴。AI連携を前提にした自動データ分類や品質ルール設定など、レイク上のデータ品質管理を強化する設計です。 Dataplexページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
AWS HealthLake /
AWS Data Exchange /
AWS Glue Data Catalog /
Google BigLake
■ 特徴と役割
- スキーマ検出やカタログ化により、レイク上のファイルを分析可能な構造に変換する
- ユーザー・ロール単位のデータ権限管理をクラウドサービスと統合
- 重複排除・分類・タグ付けなどにより、データの信頼性を高める
- 異なるクラウドやDWH間でのデータビュー統合を可能にする
■ ツール選定時のポイント
- 既存レイクとの互換性:基盤となるストレージとの統合レベルを確認する
- データガバナンス要件:セキュリティポリシー、データライセンス、アクセス権限管理の自動化対応状況を確認
- カタログの拡張性:ETLツールやBIツールから参照できるAPI・接続性が十分かを評価
- ベンダーロックイン回避:AWS専用/GCP専用機能に依存しすぎると、マルチクラウド構成で制約になる場合がある
ベクトルDB
ベクトルDBは、テキスト・画像・音声などの非構造データをベクトル化し、高次元空間で類似度検索を行うためのデータベースです。
生成AIや検索の文脈で急速に注目されており、従来のRDBやDWHでは扱いづらい「意味的な近さ」に基づく検索を実現します。
■ このカテゴリのツール例
| Pinecone | クラウドネイティブなベクトルDBの代表格で、LLMアプリケーション向けに最適化されたスケーラビリティと低レイテンシを提供。
APIベースで容易に統合でき、データ更新や削除にも強く、運用管理を開発者が意識せずに済むマネージド設計が特徴です。 Pineconeページはこちら |
|---|---|
| Weaviate | オープンソースのベクトルDBで、スキーマ定義・GraphQLクエリ・モジュール拡張による柔軟性が高い。
自動ベクトル化機能(内蔵モジュールでのエンコーディング)を持ち、エンジニアでなくてもAI検索を構築しやすい点で差別化されています。 Weaviateページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
Milvus /
LanceDB /
Vespa /
Activeloop Deep Lake /
Chroma Vector Database /
Zilliz /
Qdrant
■ 特徴と役割
- テキストや画像などの非構造データを「意味的な特徴量(ベクトル)」で格納し、類似度検索を実現する
- LLMや生成AIアプリケーションにおけるRAG構成の中核を担う
- 検索・推薦・クラスタリングなど、AI推論前処理や知識ベース構築に活用される
- 一般的なSQLベースDBでは困難な「曖昧検索」や「意味検索」を可能にする
■ ツール選定時のポイント
- ベクトル数・次元数・クエリ頻度などに応じたスケーラビリティとインデックス構成の最適化が必要
- 検索精度と速度のバランス(近似検索のアルゴリズム選択)がユースケースによって異なる
- 統合容易性:LLMやEmbeddingsモデルとの連携API、Python SDKなどの開発者体験の良さ
- 運用環境:マネージド型(Pinecone)か自前運用型(Milvus、Weaviate)かによる運用コスト差
リアルタイム分析DB
リアルタイム分析DBは、ストリーミングデータや頻繁に更新されるデータを即時に集計・分析するためのデータベースです。
従来のDWHが「バッチ処理による過去分析」に強いのに対し、本カテゴリは「秒単位での状況把握」や「アプリケーション内の即時可視化」を主眼としています。
■ このカテゴリのツール例
| TiDB | TiDBは、トランザクション処理と分析処理を両立するハイブリッド型データベースです。MySQL互換を保ちながら、リアルタイム集計や大規模クエリをスケールアウト構成で高速に処理できる点が特徴です。 TiDBページはこちら |
|---|---|
| ClickHouse | カラム指向で圧倒的なクエリ性能を誇るOSSの分析DB。OLAP用途に強く、リアルタイム集計・ダッシュボード処理で世界的な採用実績を持つ。
単体性能では最速クラスだが、トランザクション性や更新頻度の高いデータ処理にはやや不向き。 ClickHouseページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
AlloyDB /
CrateDB /
Druid /
Azure Data Explorer /
Amazon Timestream /
SingleStore /
Materialize /
QuestDB /
TimescaleDB /
StarTree /
KX /
Tinybird /
Apache Pinot /
CelerData Cloud /
Imply /
TigerData
■ 特徴と役割
- ストリーミング入力データをほぼリアルタイムで集計・可視化できる
- ダッシュボード・モニタリング・レコメンドなど「秒単位の意思決定」を要する場面で活用
- OLAP処理に特化したカラム型ストレージ構造で、高速スキャン・集計を実現する
- クラウドネイティブアーキテクチャやインメモリ処理の採用により、スケールアウトが容易
■ ツール選定時のポイント
- ユースケースの明確化:リアルタイム性重視か、汎用分析性能重視かで選択が分かれる
- データ更新頻度とクエリの性質:頻繁な更新・結合が多い場合はSingleStoreやTiDBなどのHTAP型が有利
- ストリーミング基盤との統合性:KafkaやKinesisなどとの接続が容易かを確認する
- コスト・運用負荷:OSSかマネージドかによりTCOが大きく異なる
クエリエンジン
クエリエンジンは、分散データやデータレイク上の膨大なデータに対して、SQLベースで即時クエリを実行できる処理基盤です。
DWHとは異なり、データを移動せずに直接問い合わせできる点が特徴で、クラウドネイティブ環境での分析やマルチソース統合に活用されます。
■ このカテゴリのツール例
| Trino | OSSの分散SQLクエリエンジンで、複数のデータソースに対して透過的にクエリを実行可能。大規模データに対して高速でスケーラブルな分析ができる点が強みで、オンプレやクラウドのデータレイク統合で広く採用されています。 Trinoページはこちら |
|---|---|
| Dremio | クエリの最適化機能とデータキャッシュに強みを持つOSS/商用の分析プラットフォーム。データ仮想化とアクセラレーションを組み合わせることで、複数ソースの統合分析を低レイテンシで実現できます。 Dremioページはこちら |
💡他にも下記ツールがあります
Amazon Athena /
Qubole /
Starburst /
Apache Hive /
Apache Kylin
■ 特徴と役割
- データを移動せずに複数ソース(データレイク・DWH・RDB)に対して直接クエリ可能
- SQLを標準インターフェースとして提供し、データ分析者にとって学習コストが低い
- キャッシュ・マテリアライズドビュー・分散処理で高速なクエリ応答を実現
- データ統合・可視化基盤の前段として、BIやダッシュボードの即時分析に活用
■ ツール選定時のポイント
- 接続可能なデータソース:利用しているDWH・データレイクとの接続可否を確認
- パフォーマンス要件:分散処理・キャッシュ機能によりクエリ応答速度が変わるため、SLAsとの整合性を確認
- 運用負荷:OSS型かマネージド型かで運用コストが大きく変わる
- セキュリティ・ガバナンス:アクセス制御や監査ログ対応が可能かを事前確認
終わりに
分析向けデータベースは、データを単に格納するだけでなく、必要な情報を即座に取り出し、ビジネスやプロダクトの意思決定に活かすための基盤です。
適切に設計・運用されたDBは、組織の意思決定スピードやサービス改善の効率を大きく高める強力な武器となります。
本カオスマップでは、分析向けDBや関連基盤ツールをカテゴリごとに整理し、それぞれの特徴や選定ポイントをまとめました。特定ツールを推奨するのではなく、自社の利用目的やフェーズに応じた現実的な選択の参考としてお役立ていただければ幸いです。
お読みいただき、ありがとうございました。