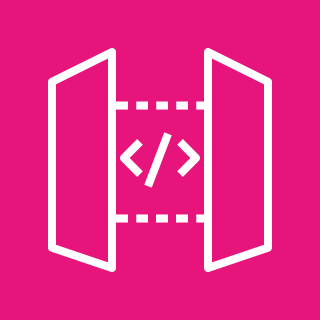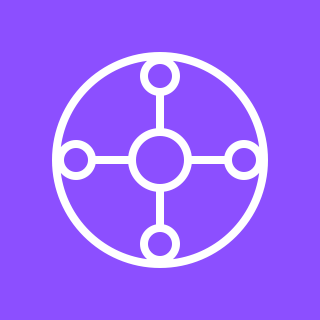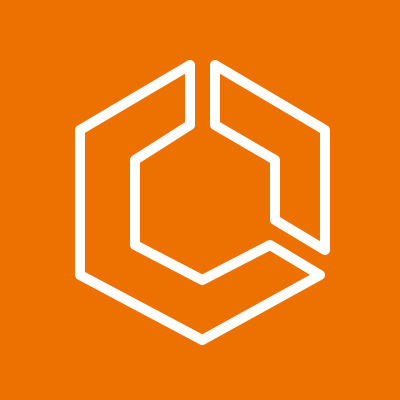「fincode byGMO」の決済基盤アーキテクチャ
アーキテクチャの工夫ポイント
fincodeは急成長するスタートアップ/ベンチャーのお客さまを多く抱えるため、サブスクリプション機能などの決済周辺機能の積極的な利用を想定したり、決済リクエストの急増に耐えるためのスケーラビリティを確保したりしつつ、カード情報を管理するためのセキュリティ基準である『PCI-DSS』への完全準拠が可能な、非常に高いレベルでセキュアである設計が求められます。
fincodeの基盤はオンプレミス基盤とクラウド基盤から成るハイブリッド構成です。
前者はGMO-PG連結企業集団全体の決済処理を長らく支えてきた信頼性のある決済基盤で、後者はECS/Fargateによりフルマネージされたコンテナアプリを中心とした、今どきのAWS基盤です。fincodeの開発チームは後者の開発・運用を行っています。
AWS基盤の方では高いレベルでセキュアかつスケーラビリティが担保されたサービスにするために以下のようなアプローチを採用しています。
- マイクロサービスアーキテクチャとマルチAZ、ECS/Fargate活用による冗長性と拡張性の確保
- DynamoDBを活用したリアルタイム流量制御
- EventBridgeとStep Functionsを活用し、各バッチ処理を独立してスケーリングできる安定した実行基盤を構築。
- PrivateLinkなどVPCエンドポイントを経由させた閉域アクセスによりPCI-DSS要件に適合しつつ、AWS内の通信を高速・安定化。
- Webhook通知を独立したECSタスクとして運用することで負荷を分散し、クリティカルな処理の安定性を確保。
これらが土台となり、決算説明会資料で開示した通り前年同期比406.3%の売上成長、つまりはお客様の急速な成長の支援を実現できています。
現在のアーキテクチャの課題と今後の展望
現状のfincodeはユーザー企業のトランザクション量が多くなると、管理画面上でのその情報の参照ができないという挙動が発生することがあります。データベース周りの負荷分散やクエリの効率化などはモダンなユーザー体験の提供というfincodeのテーマの上で解決しなければならない明確な課題です。
また、今後fincodeはプレスリリースで打ち出した通り、単なる決済インフラではなく企業間決済プラットフォームとしての機能を搭載したマルチFinTechインフラとしての進化を計画しています。
fincodeというサービスの中に決済代行事業ではない新たな事業ドメインを抱えることになるため、適切なサービスの分散・冗長化というお題目をより一層意識する必要があります。
◆執筆:
GMOペイメントゲートウェイ システム本部 関連事業サービス統括部 イプシロンサービス室長 米山 純司
GMOイプシロン fincode byGMO プロダクトマネージャー 中谷 仁貴
アーキテクチャを構成するツール
会社情報

GMOペイメントゲートウェイ株式会社
GMOペイメントゲートウェイ株式会社は、オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は20兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。 決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL(Buy Now Pay Later)、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。(2025年3月末時点、連結数値)