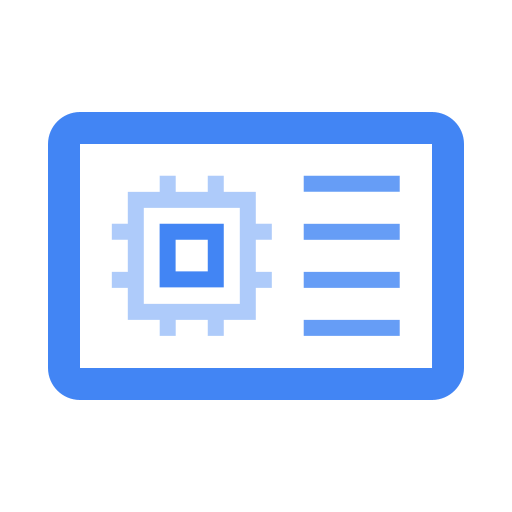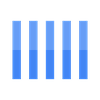LLMによる非同期文章レビュー基盤アーキテクチャ
アーキテクチャの工夫ポイント
アーキテクチャ選択の背景や意図
今回のアーキテクチャ設計では、主に3つの課題を考慮しました。
LLMの不確実性
LLMはAPIのRate Limitやレイテンシが不安定であり、システムの安定稼働において大きな懸念点でした。
組織間の連携
プロダクト組織とデータ組織が関わるため、両者の責任境界を明確にする必要がありました。
マルチクラウド環境
プロダクト組織がAWS、データ組織がGoogle Cloudを利用しており、セキュアな通信を確立する必要がありました。
これらの課題に対応するため、以下の設計方針を採用しました。
まず、LLMの不確実性に対しては、処理の失敗を前提としたリトライ(再試行)機能を持つ非同期処理を基本としました。
次に、組織間の連携については、それぞれが独立して開発・運用できるよう疎結合な構成を目指しました。
そして、AWSとGoogle Cloud間の認証については、通信の向きをAWSからGoogle Cloudへ一方向に統一し、Workload Identityを利用することで、サービスアカウントキーなどを直接管理しないセキュアな連携を実現しています。
現在の課題と今後の改善予定
現在の主な課題は、「実験→デプロイ→モニタリング→改善」という一連のサイクルを支える基盤機能が不足している点です。
例えば、データサイエンティストが考案したプロンプトやアルゴリズムを、容易に実験・デプロイできる仕組みが整っていません。
また、システムのインターフェースがCloud TasksとPub/Subに分かれており、構成が複雑になっている点も改善したいと考えています。
これらの課題を踏まえ、今後の改善項目として以下を計画しています。
インターフェースの統一
現在2つに分かれているインターフェースを、gRPCまたはREST APIに統一し、よりシンプルで管理しやすい構成を目指します。
アーキテクチャの最適化
複数のLLMを効率的に利用できるよう、アーキテクチャの最適化を進めます。
LLMOpsの導入
実験環境と本番環境をシームレスに連携させるLLMOpsの仕組みを導入し、開発サイクルの高速化を図ります。
Observabilityの向上
分散トレーシングなどを導入し、システムの可観測性を高めることで、問題発生時の迅速な原因究明を可能にします。
◆執筆:斎藤知之 @tomoppi_31
アーキテクチャを構成するツール
会社情報

株式会社タイミー
株式会社タイミーは、スキマバイトサービス「Timee〈タイミー〉」を開発・運営している会社です。 「一人ひとりの時間を豊かに」をビジョンに掲げ、人生の可能性を広げるインフラ作りに挑戦しています。
株式会社タイミーの利用ツールレビュー
BI

Lookerで全社のデータ活用を推進した話
株式会社タイミー / Tatsuya Mihashi
メンバー / データアナリスト
IaC

Terraform Providerを自作して、Devinのナレッジを整理してみた話
株式会社タイミー / hiroshi.tokudomi
メンバー / インフラエンジニア / 従業員規模: 1,001〜5,000名 / エンジニア組織: 101名〜300名
統合監視プラットフォーム

株式会社タイミーにおけるDatadog活用事例
株式会社タイミー / MoneyForest
メンバー / インフラエンジニア / 従業員規模: 1,001〜5,000名 / エンジニア組織: 101名〜300名